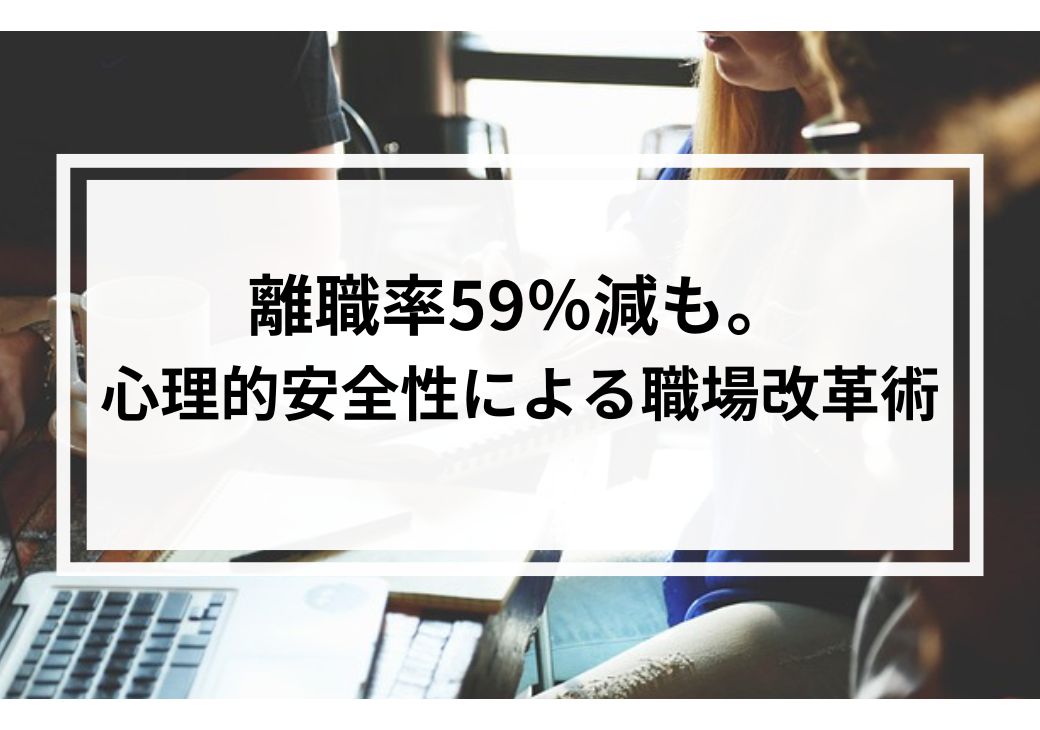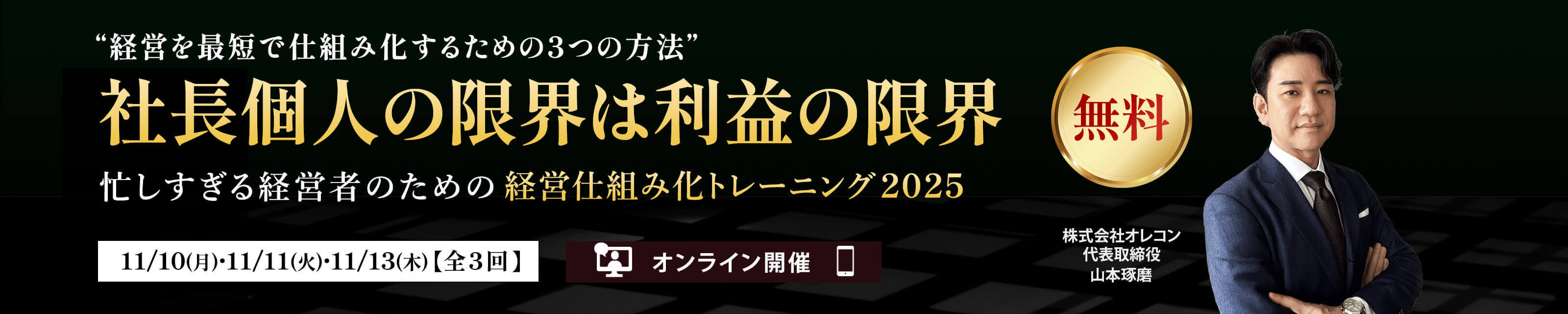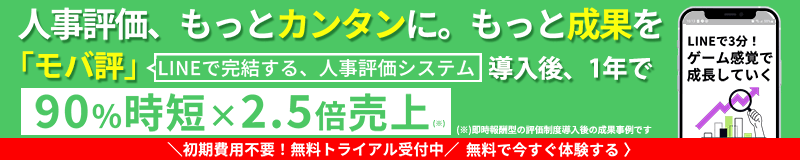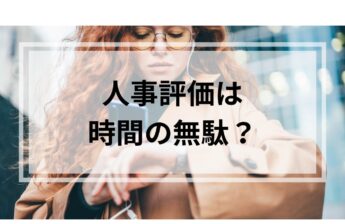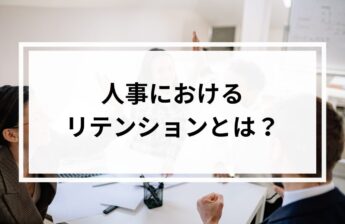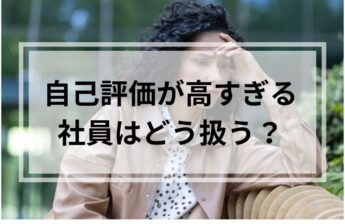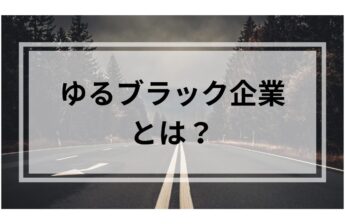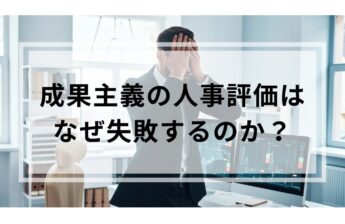心理的安全性とは?職場での重要性

心理的安全性の定義と概要
心理的安全性(psychological safety)とは、組織やチームの中で自分の意見や質問、懸念を表明しても、拒絶されたり罰せられたりする心配がないと感じられる状態を指します。
この概念は、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授が1999年に提唱しました。
つまり、「間違っても大丈夫」「知らなくても恥ではない」と思える環境のことです。従業員が安心して自己表現できることが、健全な組織運営の土台となります。
心理的安全性の概念は、単に「仲が良い」状態とは異なります。厳しい意見や率直な指摘も受け止められる関係性の中でこそ、本質的な安全性が成立するのです。
表面的な“和やかさ”ではなく、深いレベルでの信頼と対話の土壌が求められます。
なぜ職場で心理的安全性が求められるのか?
昨今の複雑で変化の早いビジネス環境では、チームメンバーが意見やアイデアを自由に出し合うことが不可欠です。
そこに心理的安全性があると、リスクを取ることや新しい提案がしやすくなります。
たとえば、業務改善のアイディアを思いついても「こんなこと言って大丈夫だろうか…」と不安が先に立ち、意見を飲み込んでしまう社員が多い職場は、改善のチャンスを逃してしまいがちです。
また、心理的安全性のない環境では、問題が隠される傾向が強くなります。ミスや不正が表面化せず、結果として経営リスクの拡大につながるケースもあるのです。
一方で、心理的安全性が確保されていれば、こうしたアイディアや問題提起が自然と表に出てくるようになります。
経営層にとっても、現場のリアルな声を吸い上げるための大きなメリットとなるでしょう。
企業の生産性・エンゲージメントへの影響
心理的安全性が高い職場では、従業員満足度やエンゲージメントが向上し、結果として離職率の低下や生産性の向上につながります。
実際、米ギャラップ社の調査によると、従業員が「自分の意見を尊重されている」と感じている職場では、生産性が21%向上し、離職率も59%低下したというデータがあります。
加えて、心理的安全性は“自律性”を促す効果もあります。指示待ちではなく、自ら考え行動できる人材が育つ環境に変わっていくのです。
さらに、エンゲージメントの高い従業員は、顧客満足度やサービス品質にも良い影響を及ぼします。社内の風通しを良くすることが、社外への価値提供にも直結するということです。
心理的安全性が低い職場と高い職場の違い

心理的安全性が低い職場の特徴
- 上司の顔色をうかがって発言する
- ミスを恐れて沈黙する
- 建設的な意見が出ない
- 「言わないほうが楽」と思っている
このような職場では、従業員は本音を押し殺し、形式的な会話しか交わしません。一見穏やかな空気でも、実際は閉塞感に包まれています。
結果として、新しいアイディアや問題提起が出づらくなり、組織としての停滞を招くリスクが高まります。
心理的安全性が高い職場の特徴
- 「わからない」と言える空気がある
- 立場を超えて対等な対話ができる
- ミスを共有して学び合う文化がある
- フィードバックが前向きに機能する
心理的安全性の高い職場では、個々の考えや経験が共有されやすく、組織としての学習力が高まります。
結果として、変化への対応力や創造性が向上し、継続的な成長が実現可能になります。
ぬるま湯組織との違い(心理的安全性と甘やかしの違い)
「心理的安全性=甘やかし」と思われがちですが、それは誤った認識です。
心理的安全性とは、挑戦や失敗を前向きに受け止め、責任を共有できる環境を指します。厳しさを失うのではなく、建設的な対話と信頼のある関係性を築くことです。
一方で、甘やかしは「相手の責任や課題を過度に軽く扱い、成長の機会を奪うこと」です。
つまり、心理的安全性は挑戦や成長を支える土台であり、甘やかしは成長を妨げる過保護な対応となります。

職場の心理的安全性を作る4つの要素
では、職場の心理的安全性を作るためには何が必要でしょうか。以下が、代表的な4つの要素です。
信頼関係の構築
心理的安全性の起点は、メンバー同士の信頼にあります。
業務の枠を超えた人間関係の構築が、率直なやりとりの土台になります。たとえば、日常の挨拶や雑談、ランチミーティングなどの非公式な交流によって、心理的な距離が縮まります。
信頼関係は一朝一夕では築けませんが、日々の小さな接点の積み重ねが大きな違いを生み出すのです。
率直なコミュニケーション
「これは言ってもいいのか」という迷いがない状態をつくるには、トップやマネージャーが率先して率直に語る姿勢が欠かせません。
さらに、「伝え方」のスキルも重要です。否定ではなく提案に変える、相手の意図を汲んでから応答するなど、思いやりのあるやりとりが心理的安全性を支えます。
挑戦を許容する文化
イノベーションの土壌には、「失敗を許容する文化」が不可欠です。
心理的安全性がある職場では、失敗を責めるのではなく、「何を学んだか」「次にどう活かすか」が重視されます。
結果よりも行動の意図に焦点を当てることが、挑戦意欲を後押しするのです。
リーダーの関与と支援
リーダーの姿勢が、職場全体の心理的安全性を大きく左右します。
部下が話しやすい雰囲気を作る、意見を遮らず傾聴する、感謝の意を表す——。こうした「小さな行動の積み重ね」が、組織全体に安心感をもたらします。
特に1on1や日報コメントなど、日常的なコミュニケーション機会を見直すことが第一歩です。
心理的安全性が高まることによる5つのメリット
職場の心理的安全性が高まると、以下のようなメリットがあります。
業務効率の向上
報告・連絡・相談が滞らず、ミスや遅延が減少します。
心理的安全性の高い組織では、「今、困っていること」や「不明点」を早期に共有できるため、手戻りが減り、無駄なコストも削減されます。
従業員満足度・エンゲージメント向上
「自分の意見が受け入れられる」と実感できる職場は、仕事への誇りや帰属意識が高まります。
これは、給与や福利厚生では補いきれない深い満足感を生み出します。
イノベーションの促進
新しいアイディアが自然と湧き上がるのは、「否定されない」という前提があるからこそ。
多様な意見が混ざり合う環境が、革新的な発想を後押しします。
離職率の低下
「安心して働ける」「相談できる人がいる」ことは、従業員が長く働きたいと感じる大きな理由です。
心理的安全性は、定着率向上の強力な要因です。
チームワークの強化
互いに信頼し、補完し合えるチームは、成果に直結します。
チーム間の壁もなくなり、共通の目的に向かって協力できる体制が整います。
【事例付き】心理的安全性を高める具体的な取り組み

成功事例
「効果的なチームとは何か?」を科学的に解明しようとした、Google社内の研究プロジェクト「プロジェクト・アリストテレス」は、心理的安全性の高さが最もパフォーマンスの高いチームの共通項であると示しました。
日本国内では、サイボウズが「多様性」と「対話」をキーワードに組織風土を改革し、働きやすさと成果の両立を実現しています。
これには、社員の声を拾い上げる仕組みや、心理的負荷を軽減する工夫が随所に見られます。
エンパワーパス流の心理的安全性向上策(オレコン式評価・採用の視点から)
エンパワーパスでは、オレコン式の評価制度を通じて、社員が安心して意見を述べられる環境づくりに取り組んでいます。
ここでは、心理的安全性を高めるオレコン式評価制度について、その一部を紹介します。
- 評価の透明性と納得感がある
曖昧さを排除し、「誰が・何を・どのように」評価されるかが明確。 - 行動レベルの「小さな成功体験」を積ませる設計
評価項目が細かくステップ化されており、新人でも「できた!」が積み重なる。
小さな前進がすぐに認められることで、自己効力感(やればできる感覚)を持てる。
恣意的な判断がないため、不公平感が減り、安心して働ける。 - 失敗を隠さず、報告・改善が奨励されている
「ミスを報告しても大丈夫」「改善策を出せば評価される」仕組みがあるため、心理的に安心してチャレンジできる。
評価項目に「ミスを隠さず報告&自ら改善」と明記されているのが特徴。
心理的安全性を高めるには、制度と日々の行動や環境が連動している必要があります。
軸となる「評価制度」の詳しい設計については、下記の資料をご覧ください。
評価制度の仕組み化からタスク管理の標準化まで、具体的な方法を無料でご提供します。
採用の視点から心理的安全性を高めるには

心理的安全性の高い職場づくりは、実は採用の瞬間からすでに始まっています。
どれだけ素晴らしい制度や環境を整えても、そこに集まる人が“安心して関われる人材”でなければ、真の心理的安全性は育ちません。
そこで注目されているのが、スキルや経歴だけでなく、価値観・対話力・成長意欲といった“人の本質”を見極めるポテンシャル採用です。
このアプローチは、社員が信頼し合い、率直に意見を交わせるカルチャーを築くための強力な土台になります。
ポテンシャル採用については、こちらの記事で紹介しています。
心理的安全性を向上させるために注意すべきポイント

心理的安全性とパワハラの境界線
心理的安全性とは、「何でも言っていい」ということではありません。
上司やリーダーの言動が、部下にとって心理的負担になることもあり、パワハラと受け取られてしまう危険性もあります。
- 心理的安全性とは:職場で自分の意見やミスを安心して話せる状態
- パワハラとは:相手の尊厳を傷つけたり、精神的な圧力を与える行為
両者の境界線は、「伝え方」と「意図」にあります。
たとえ厳しい指摘でも、相手を尊重し、成長を目的に伝えるなら心理的安全性を保てます。しかし、人格を否定したり、感情的・一方的な言動はパワハラに当たる可能性があります。
つまり、相手が安心して受け取れるかどうかが、大きな分かれ道になります。
短期間での変革は難しい?長期的な視点の重要性
組織文化の変化は時間がかかります。評価制度や研修だけで解決するものではなく、日々のコミュニケーションとリーダーの姿勢が問われるのです。
「まずは自分から」変わることで、周囲も少しずつ変わっていきます。継続的な取り組みが成果につながることを意識しましょう。
部下から慕われるリーダー像については、下記の記事をご覧ください。
まとめ

職場の心理的安全性を向上させるために必要なこと
・信頼と率直さを土台とする人間関係の再構築
・挑戦と失敗を許容する組織文化の確立
・リーダー自身の関わり方の見直し
どれも、今日から少しずつ始められるものばかりです。
企業・経営者が今すぐできるアクション
心理的安全性のある職場づくりは、制度や環境に加えて、経営者・リーダーの関わり方から始まります。
まずは、次の“小さな一歩”を意識することが大切です。
- 「意見を歓迎する」姿勢を明言する
- 部下の発言をさえぎらず、感謝と傾聴を心がける
- 失敗や不安を共有してもよい空気を自らつくる
- 社内アンケートや評価項目を見直し、“安心して話せる環境”を可視化する
こうした日常の積み重ねが、組織全体に「意見を言っても大丈夫」という安心感を広げていきます。
まずは自分の行動から見直すことが、職場の空気を大きく変える第一歩です。
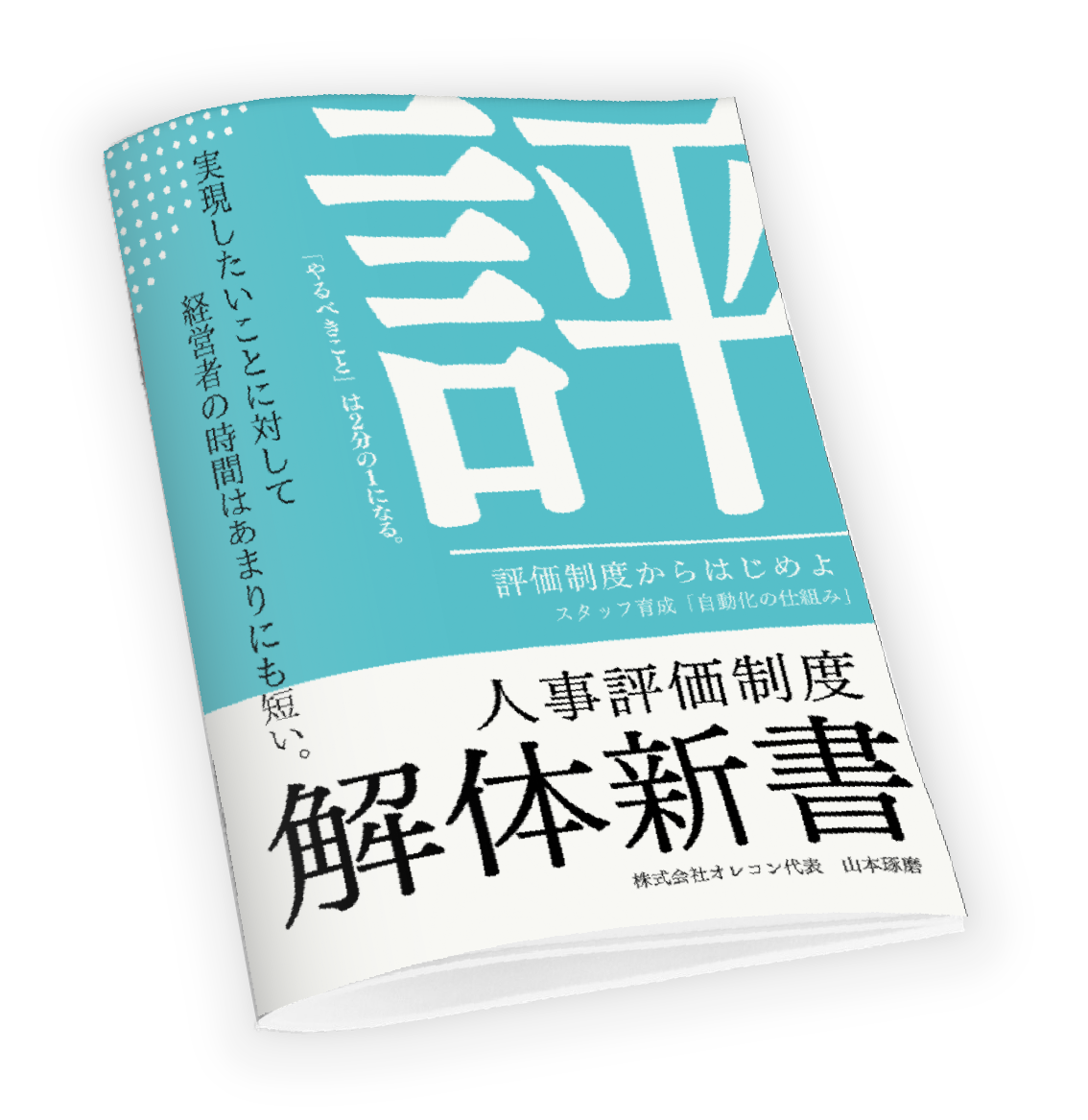
人材が定着し、成果を出す仕組みの作り方