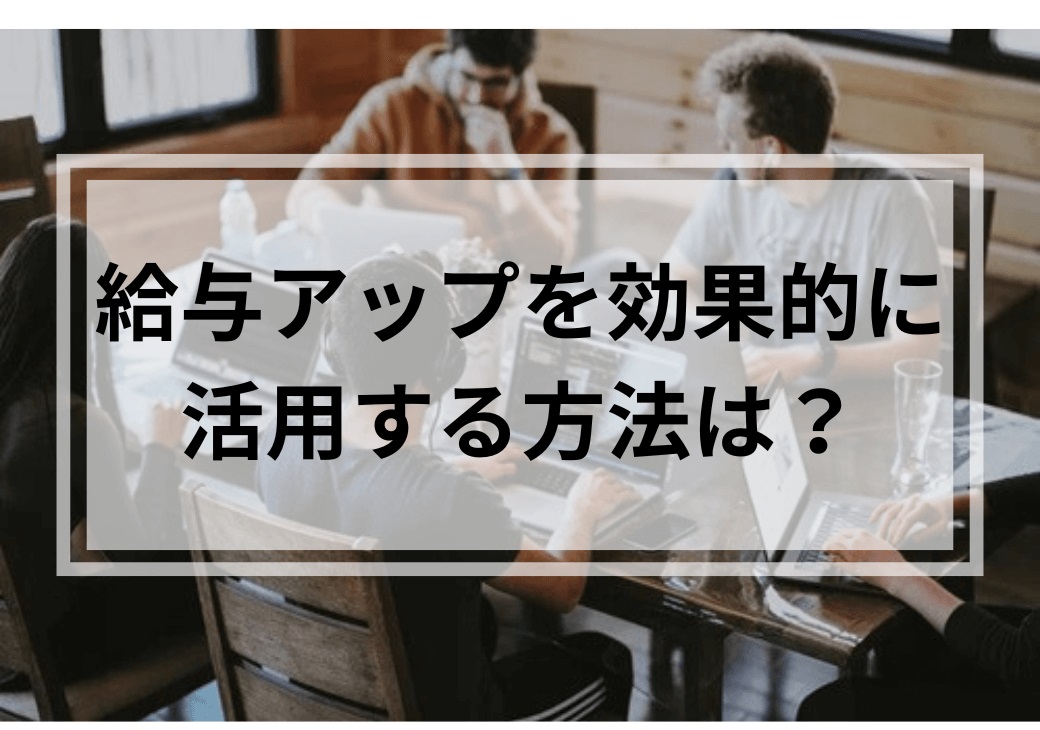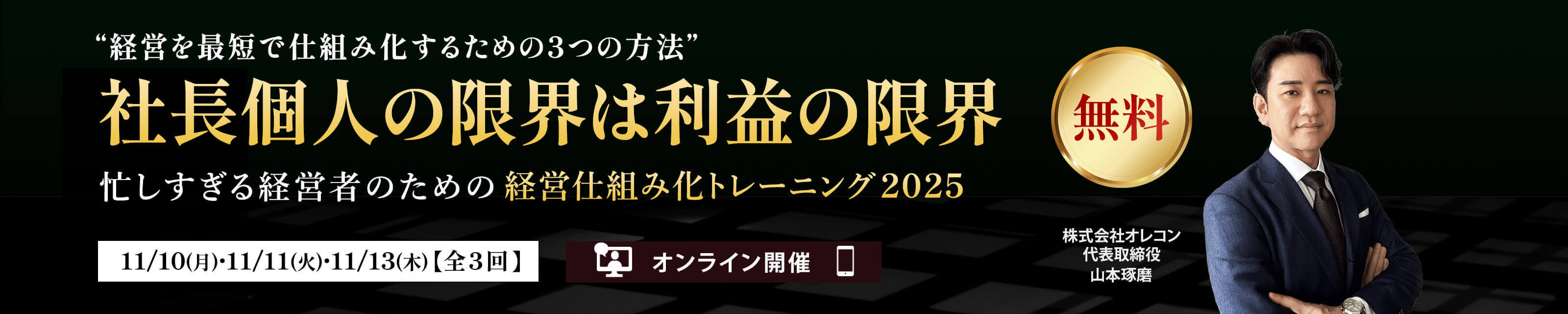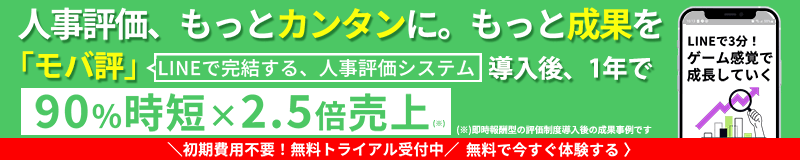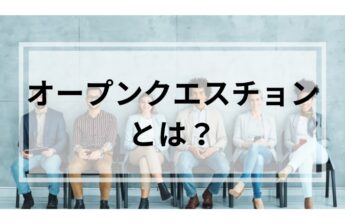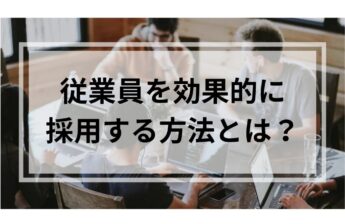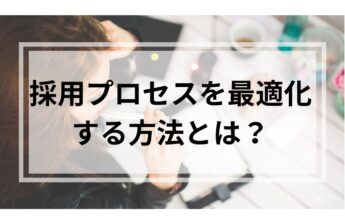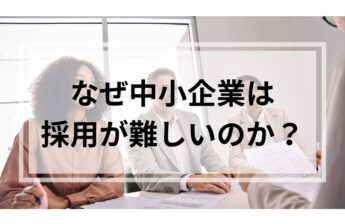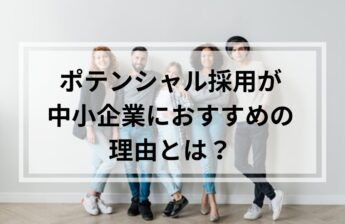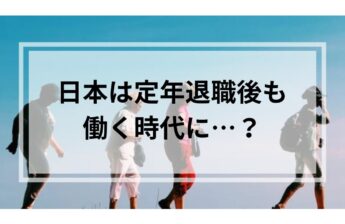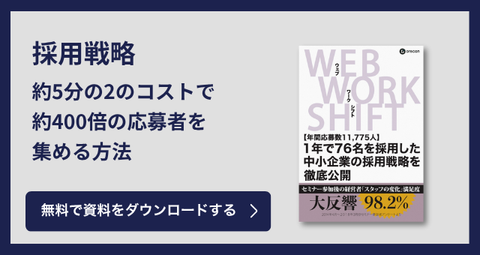給与における種類の違い

給与には、いくつかの種類があります。これらは具体的に何が違うのでしょうか?
簡単に下記にまとめています。
定期昇給
一般的に、社員の勤続年数や年齢に応じて昇給すること。社員個人のスキルや実績よりも勤続年数が給与アップにつながることが多い。
ベースアップ
全社員の個別の給料水準が一律に引き上がること。賃金表の書き換えになるため、勤続年数や役職に関わらず全社員の給料がアップする傾向にある。
賞与
会社の業績によって、固定された給与とは別に支払われる報酬のこと。これは定期的に支払われるものではない。
給与を考慮する時に気を付けること

賞与は、前回の賞与額とは関係なく今回の賞与額を決めることができるため、金額の設定がさほど難しくありませんが、一方で、定期昇給、ベースアップで給与をあげた場合、その金額を引き下げることは難しいです。
従業員ごとの給与体系や評価基準を明確化し、能力や業績に基づいて公正な方法で賃金を決める必要があります。また、給与は企業の競争力にも関わるため、業界全体や地域の賃金水準、労働市場の状況を考慮して決定するといいとされています。
コストと昇給の効果

①従業員の給与が低いことで隠れているコストはないか?
従業員への賃金が少ないと、欠勤の増加、多くの離職、顧客との問題など、実は多くの隠れたコストが生じます。
以下を考えてみてください。
・退職した従業員を補充するにはいくらかかるか?
・従業員に不満を抱いたリピート顧客を失うと、どのようなコストがかかるか?
・やる気のない従業員のミスを修正すると、企業にとってどれくらいの損失があるか?
②昇給による潜在的な生産性の向上
給与の向上は、従業員にとっての報酬や評価のひとつの形態であり、それが彼らに対してより高いモチベーションや満足感を与え、仕事に対する意欲やパフォーマンスを向上させることが期待できるでしょう。
従業員は自身の能力やスキルの向上を目指し、組織の目標達成に対し、積極的に貢献することが期待されます。あなたの企業では、昇給によって従業員の生産性を引き出すことで、組織全体の成果や競争力を高めてくれるのです。
昇給を戦略的に活用するには?

Indeedでは、従業員の昇給を活用したアプローチ方法を紹介しています。
予算について透明性を保つ
昇給交渉をする場合は、あなたが提示できる内容を従業員に率直に伝えたほうがいいでしょう。あなたが従業員を大切に思い、彼らに対し最善を尽くしていることを理解してもらいます。多少の昇給であったとしても、最大限の昇給が得られると従業員が知ることで、満足感が増大するかもしれません。
基本給の代わりにボーナスを提供する
長期的にお金を節約できる習慣の 1 つは、基本給を上げる代わりに定期的なボーナスを提供することです。ボーナスの金額は、パフォーマンス、経験、その他の要因に基づいて決定されます。
定期的にボーナスを支給することで、従業員のモチベーションが高まる可能性があります。ボーナスは即座に満足感を与え、職場での生産性と成功に報いるための1つの方法です。
競合他社からヒントを得る
競合他社の、給与の種類、昇給の頻度、平均昇給の予算がいくらかなどはご存じですか?他社の情報を収集すると、新入社員を獲得するために競争したり、現在の従業員とより効果的に交渉したりするのに役立つでしょう。
昇給を一貫して維持
昇給を分配する際に公平かつ平等であることは、昇給を提示する上で重要な部分です。給与の高い従業員に高い昇給を与えたり、偏見が意思決定に影響を与えたりすると、従業員の間に摩擦、衝突、不満が生じる可能性があります。
公正な給与を提供することは、従業員の士気を高めるだけではありません。多くの場合、公正労働基準法(FLSA) などの法律により、個人に公平に支払うことが義務付けられています。
明確な基準を確立する
昇給を決定するための一連のガイドラインを確立すると、個人的な偏見の影響を軽減し、昇給の決定に責任を負うすべての経営陣が、同じ基準を使用して従業員の評価ができます。
従業員との給与に関する話し合いの際に昇給がどのように決定されたかを説明することで、偏見を持たれるリスクを軽減し、会社を守るのに役立ちます。
上記に示したように、給与の決定は優秀な人材獲得には欠かせない要素であり、企業が従業員の時間と労力を大切にしていることを示すチャンスでもあります。自社の従業員にとって、適切な給与制度はなにかを考慮し、慎重に検討してみてください。
参考: