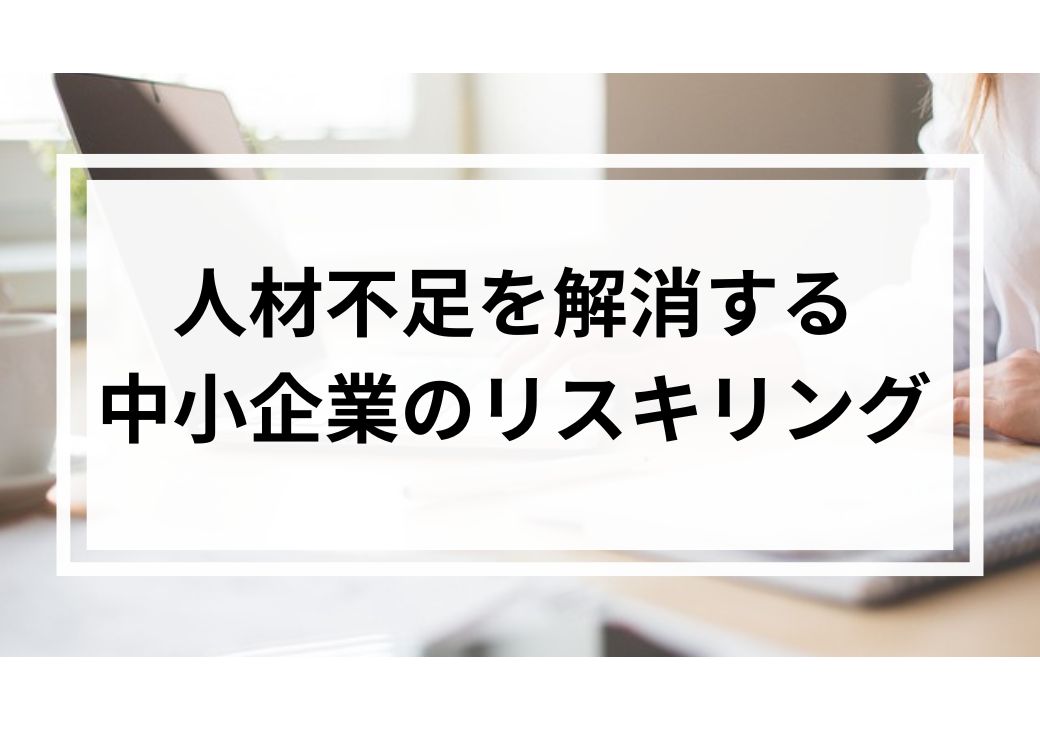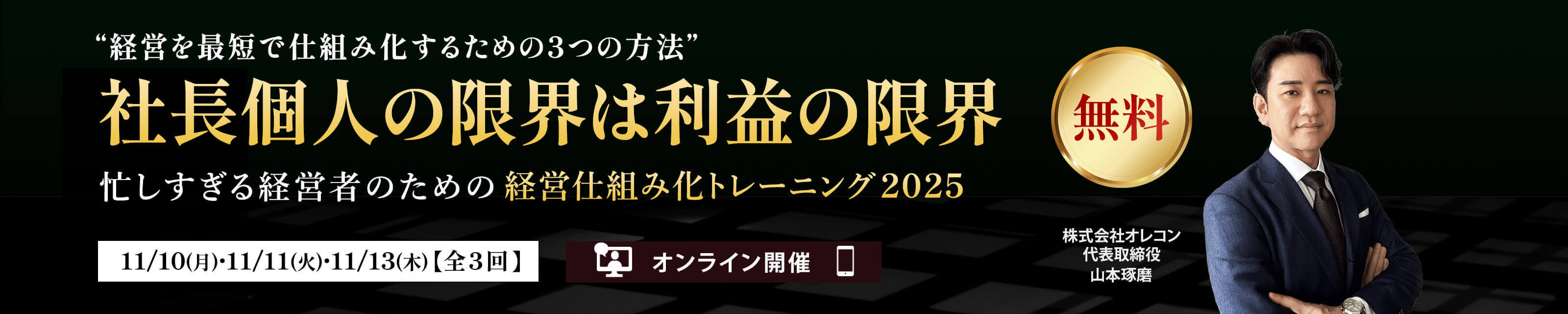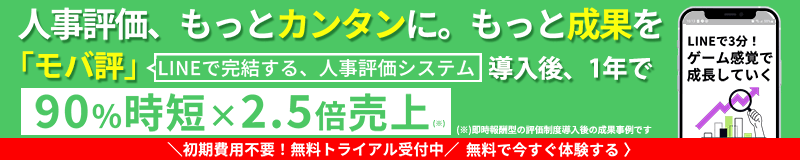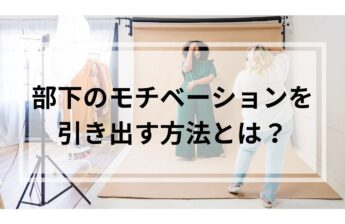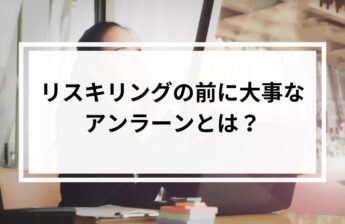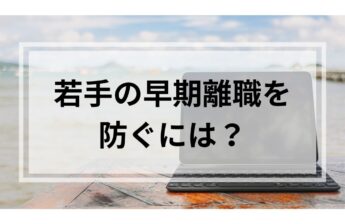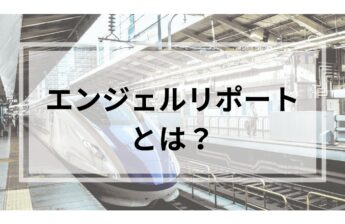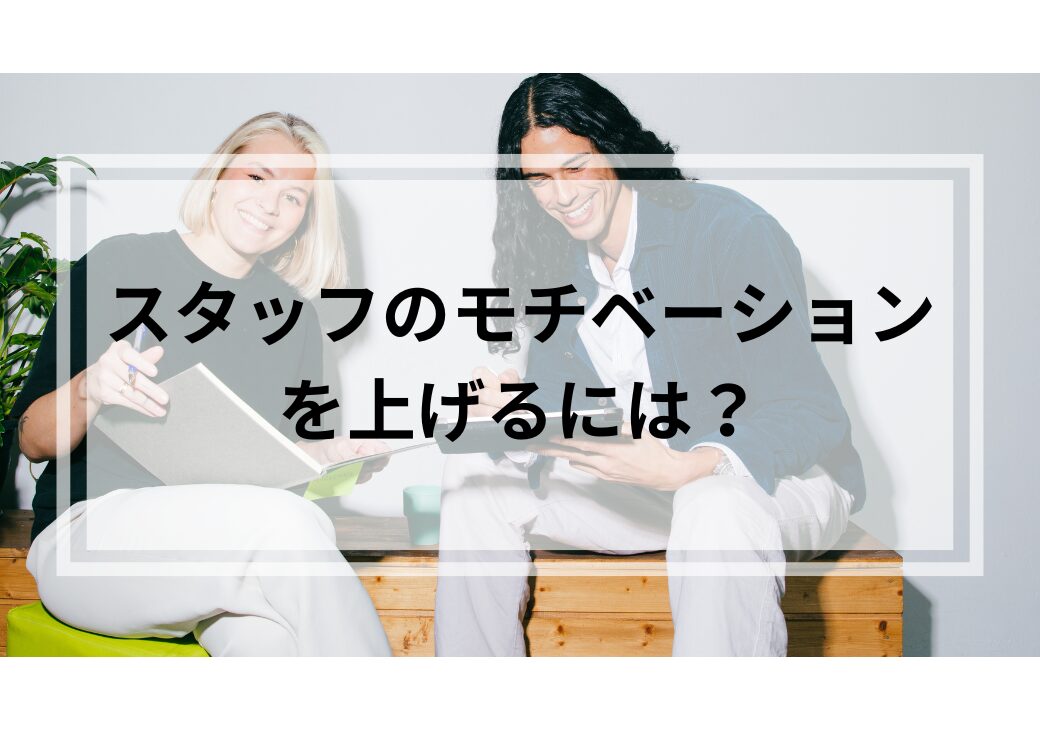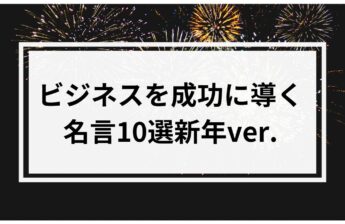リスキリングとは?

リスキリングとは、業務の変化に対応するために新たな知識やスキルを習得することです。
特に近年は、デジタル化やビジネス環境の急速な変化に対応する手段として注目されており、
政府も支援を進めています。
詳しくは、過去に掲載した「リスキリングとは?そのメリットと効果的な導入法」をご覧ください。
中小企業が注目すべき理由とメリット
それでは、なぜ今リスキリングが注目されているのか、そして、中小企業こそ取り組むべき理由やメリットについて紹介していきます。
業務効率が上がり、利益に直結する
最新の知識やスキルを身につけることで、プロジェクトのスピードアップや無駄の削減が可能になります。結果としてコスト削減やサービス品質の向上が実現し、企業の収益力が高まります。
人材不足の解消・離職率の低下
社員に学ぶ機会を提供することで、モチベーションが向上します。自分の成長を実感できるようになり、それが仕事への意欲向上やキャリア志向につながり、離職率の低下にも貢献します。
また、外部から優秀な人材を獲得することに苦労している中小企業は少なくありません。リスキリングを実施すれば、自社の従業員に新たな知識やスキルを学んでもらい、必要な人材へと育成できるので、採用コストを抑えながら人材不足に対応することができます。
社員のITスキルが会社の成長を支える
ITスキルの向上は、業務効率やデジタル化推進のカギになります。リスキリングによって、社員が新しいツールや技術を使いこなせるようになれば、生産性が高まり、競争力の強化につながります。
中小企業でもビジネスで遅れをとらないために、AI等のIT技術を使用することが現代では必須になりつつあり、従業員のITリテラシーを向上させる観点からも、リスキリングが注目されています。
中小企業におけるリスキリングの現状

中小企業のリスキリング実施率はまだ高くはありません。
リスキリングの取り組み状況は、「取り組んでいる」との回答が8.9%、「取り組みたい」は17.2%で、
リスキリングに積極的な姿勢を示した企業は合計26.1%と、およそ4分の1。
このうち、「取り組んでいる」とした企業の割合を見ていくと、大企業が15.1%で最も高く、中小企業は7.7%でした。※1
中小企業のリスキリング導入の課題
こうした、中小企業のリスキリング導入が進まない背景としては、以下のものが挙げられます。
・コストがかかる
リスキリングには、研修費や教材費などの一定のコストがかかります。中小企業にとっては負担が大きく感じられるかもしれませんが、費用を抑えるために期間を短縮したり、サポートを最小限にしたりすると、期待した成果が得られないこともあります。
社員のやる気を保つためにも、目的に合った内容と規模で、必要な予算と支援体制をしっかり確保することが大切です。
・すぐには結果が出ない
リスキリングの効果は、すぐに数字として現れるとは限りません。焦って途中でやめてしまうと、せっかくの取り組みが無駄になってしまう可能性もあります。
成果が見えにくいときこそ、社員と一緒に進捗を振り返り、学びの方法や内容を柔軟に見直すことが重要です。継続的な学習環境を整えることで、着実な成長につなげていきましょう。
・対応する時間が確保できない
中小企業では限られた人員で日々の業務を回しているため、社員をリスキリングに割く時間が確保しにくいのが現実です。
「研修のために現場を空けられない」という声も多く、学習の優先順位がどうしても下がってしまいがちです。
eラーニングやマイクロラーニングなどを使えば、スキマ時間で少しずつ学ぶことも可能です。
全体を見直して、無理のない形で学習時間を設ける工夫が求められます。
・育てた人材の流出
リスキリングによって社員が市場価値を高めると、転職による人材流出のリスクが生じることも。
そのためには、学んだスキルの活用方法を明確にし、成長実感のある環境を用意することが重要です。
あわせて待遇や評価制度を見直すことで、社員の定着と信頼を促進できます。
※1 株式会社帝国データバンクによる全国の企業対象:「リスキリング」に関する調査結果より(調査期間:2024年10月18日~31日、回答:1万1,133社)
中小企業こそAIを活用したリスキリング

AIを使ったリスキリングは、今や中小企業にとって現実的で効果的な人材育成手段です。
また、経済産業省の推計では、2030年に日本のIT人材は最大59万人不足するとされています。
外部採用だけでの対応は困難となり、中小企業はなおさら自社で人材を育てる「リスキリング」が重要となってきます。
AIリスキリングのメリット
以前は大企業向けと思われていたAIですが、今では無料・低価格のツールが充実し、補助金も活用できるため、初期費用を抑えてリスキリングをスタートさせることが可能です。
・無料・低価格ツールを活用
ChatGPT(無料版)、Google WorkspaceのAI機能、Canva、Microsoft Power Automateなど、導入コストをかけずに利用できるAIツールが充実しています。
・助成金・補助金を活用
「人材開発支援助成金」などを利用すれば、研修費用の最大75%が補助されるケースも。
さらに、 いきなり全社で導入するのではなく、小規模からの実証実験をおすすめします。
まずは一部の部署でAIを試し、成果を検証しながら段階的に広げる方法が効果的です。
スタッフのやる気と成果を最大化する秘訣を公開中!
評価制度の仕組み化からタスク管理の標準化まで、具体的な方法を無料でご提供します。
中小企業の成功事例3選

続いて、中小企業のAIを活用したリスキリング事例を見ていきましょう。
①石川樹脂工業株式会社
人手不足を機に推進したリスキリングと業務改革の取り組み
・経営者自らがリスキリングに取り組み、AIやロボット導入をスムーズに進める
・就業時間内にリスキリングを実施し、外部人材のコーチングも活用
・若手社員を中心に、EC・SNSを活用したデジタル販売を展開するなど新事業に次々挑戦
社内で20台以上のロボットを安定稼働、新事業のオンライン販売ではわずか3ヵ月でEC売上が倍増と、
リスキリングに取り組んで3年で労働生産性が2倍になりました。
従業員の給与引き上げも実現するなど、「人材不足」という中小企業共通の課題を、AIリスキリングで
乗り越えた良い事例です。
②株式会社陣屋
経営難を乗り越えるために実施したIT化と人材教育の取り組み
・社内SNSを活用し、IT導入の目的を継続的に発信
・旅館管理システム「陣屋コネクト」を自社開発し、紙台帳からの脱却
・全員にタブレットを持たせて勤怠管理や情報共有をデジタル化
老舗旅館の大胆なデジタル転換とAI活用の良い事例です。
自社開発の「陣屋コネクト」は他の宿泊施設にも展開され、600施設以上で導入されるなど、業界全体のDX・AIリスキリングのモデルケースとなっています。
シニア中心の従業員がデジタル・AI技術を使いこなせるように現場主導で学び直しを進め、業績も大きく改善。「おもてなし×AI」の新しい価値を創出しました。
③西川コミュニケーションズ株式会社
印刷業からデジタル事業への転換に向けた取り組み
・費用は会社が全額負担で全社員にAI学習を推奨
・経営者自ら先行してAIの知識を学び、社内に浸透
・継続的な学習を支える企業文化を育成
会社全体でAI・デジタル分野への大転換を成功した事例です。
社員のキャリアや希望を尊重しつつ、学びの機会と費用を惜しみなく提供することで、学び続ける組織風土を築き上げています。
AIを活用したリスキリングに取り組んだ3社をご紹介しました。
特に非デジタルな業種では、「IT・AIは難しい」という先入観が障壁になってしまいがちですが、
3社はいずれも工夫を凝らしてこの壁を乗り越えています。
中小企業のリスキリングを成功させるポイント

・経営層が“旗を振る”体制づくり

リスキリングを企業全体で推進していくには、現場任せではなく経営層が自ら旗を振る姿勢が不可欠です。中小企業においては、トップの理解とコミットメントが組織全体の動きを大きく左右します。
具体的には、「なぜ今リスキリングが必要なのか」「どのように事業成長に貢献するのか」といったビジョンを明確にし、全社員に丁寧に共有することが重要です。加えて、学習に必要な予算や時間といったリソースを戦略的に確保するなど、経営主導での仕組み構築が求められます。
・継続的に学べる“仕組み”を整える
リスキリングの成果は短期間では現れにくく、学びを続けることによって初めて業務に活かされ、組織力の向上につながります。そのためには、単発の研修ではなく、継続的に学習できる仕組みづくりが重要です。
たとえば、オンライン学習の導入や、社員同士が学び合う勉強会の開催、自主学習に対する時間確保や評価制度への組み込みなどが挙げられます。小さな取り組みでも、「学びが定着する土壌」をつくることで、社員のスキルが着実に底上げされていきます。
・個別の育成計画を立てる
リスキリングの効果を最大限に引き出すには、画一的な教育ではなく、一人ひとりに合った育成計画を立てることが重要です。社員の業務内容や将来のキャリア、現在のスキルレベルはさまざまであり、それらに即した計画でなければ意味のある成長にはつながりません。
まずはニーズ分析によって必要なスキルを明確にし、次に「何を、いつまでに、どう習得するか」といった具体的な目標を設定。そのうえで、進捗確認や評価を定期的に行うことで、成長の実感と成果を両立させることができます。
・外部の専門家や教育機関を積極的に活用する
中小企業の多くは、リスキリングを社内リソースだけで完結させるのが難しい状況にあります。そこで有効なのが、外部の専門家や教育機関の知見を活用することです。
たとえば、人材育成のノウハウを持つコンサルタントに制度設計を依頼したり、専門スクールやeラーニングプログラムを導入したりすることで、限られた人員でも質の高い学びを実現できます。また、国や自治体による補助金制度を活用すれば、コストの負担を軽減しながら、外部リソースの導入がしやすくなります。
中小企業が活用できる補助金・助成金制度

中小企業がリスキリングを推進する際には、国や自治体の補助金制度を上手に活用することで、費用面の負担を軽減しながら人材育成を加速することができます。以下に、特に活用しやすい主要な制度を紹介します。
・DXリスキリング助成金(東京都)
東京都が提供するこの助成金は、中小企業や個人事業主を対象に、DX(デジタルトランスフォーメーション)に必要なスキル習得を目的とした研修費用やeラーニングの利用に対して助成が行われます。
たとえば、「生成AIの活用研修」や「SaaSツールの操作教育」なども対象となっており、OFF-JT(職場外研修)を10時間以上実施することが条件です。
・人材開発支援助成金(厚生労働省)
厚生労働省が実施するこの制度は、企業が社員に専門性の高いスキルを身につけさせるための研修を実施した際に、教育訓練にかかった費用と受講中の賃金の一部を補助する制度です。
社員のキャリア形成や、業務の高度化に向けた取り組みに適しています。
・IT導入補助金(通常枠)
中小企業が業務効率化のためにITツールを導入する際、導入費用の2/3〜4/5が補助される制度です。SaaS導入だけでなく、社員向けの操作研修も補助対象になるため、AIツールやクラウドサービスを業務に定着させるための教育とセットで活用できます。
・省力化投資補助金
この制度は、AIやロボティクスなどの省力化技術を活用した設備投資とあわせて、社員の研修も補助対象に含めることができる制度です。
たとえば、RPAツールと生成AIを組み合わせた業務自動化の導入時に、操作トレーニングを行うと補助対象となります。
上記以外にも、地方自治体が独自に実施している補助金制度や支援プログラムがあります。
地域特化型のデジタル人材育成プログラムや、研修費用補助、専門家派遣など、内容は多岐にわたるため、自社の所在地に応じてこまめに情報収集を行うことが大切です。
まとめ
リスキリングは、単なるスキルアップではなく、企業の持続的な成長や競争力の強化を実現するための戦略的な投資です。
とくに中小企業にとっては、急速に変化する市場やテクノロジーの波に対応していくうえで、限られた人材資源を最大限に活かす手段ともいえます。
補助金などを上手く活用して、中小企業もリスキリングに取り組みましょう。
***
弊社オレコンの評価制度には、約280項目にわたる評価指標があり、その中にはリスキリング要素を含む
項目も数多く組み込まれています。
たとえば
「AIや解析ツールを活用して数値改善を図る」
「景品表示法を学び、自社媒体の表記チェックを行う」
など、日々の業務を通じて新たな知識やスキルを自然に身につけられる設計です。
リスキリングの推進には、学びを継続できる“仕組み”が欠かせません。
オレコンの評価制度は、社員の成長とスキル習得を同時に実現する土台となっています。
▼評価制度の全体像や評価項目例を知りたい方はこちらから
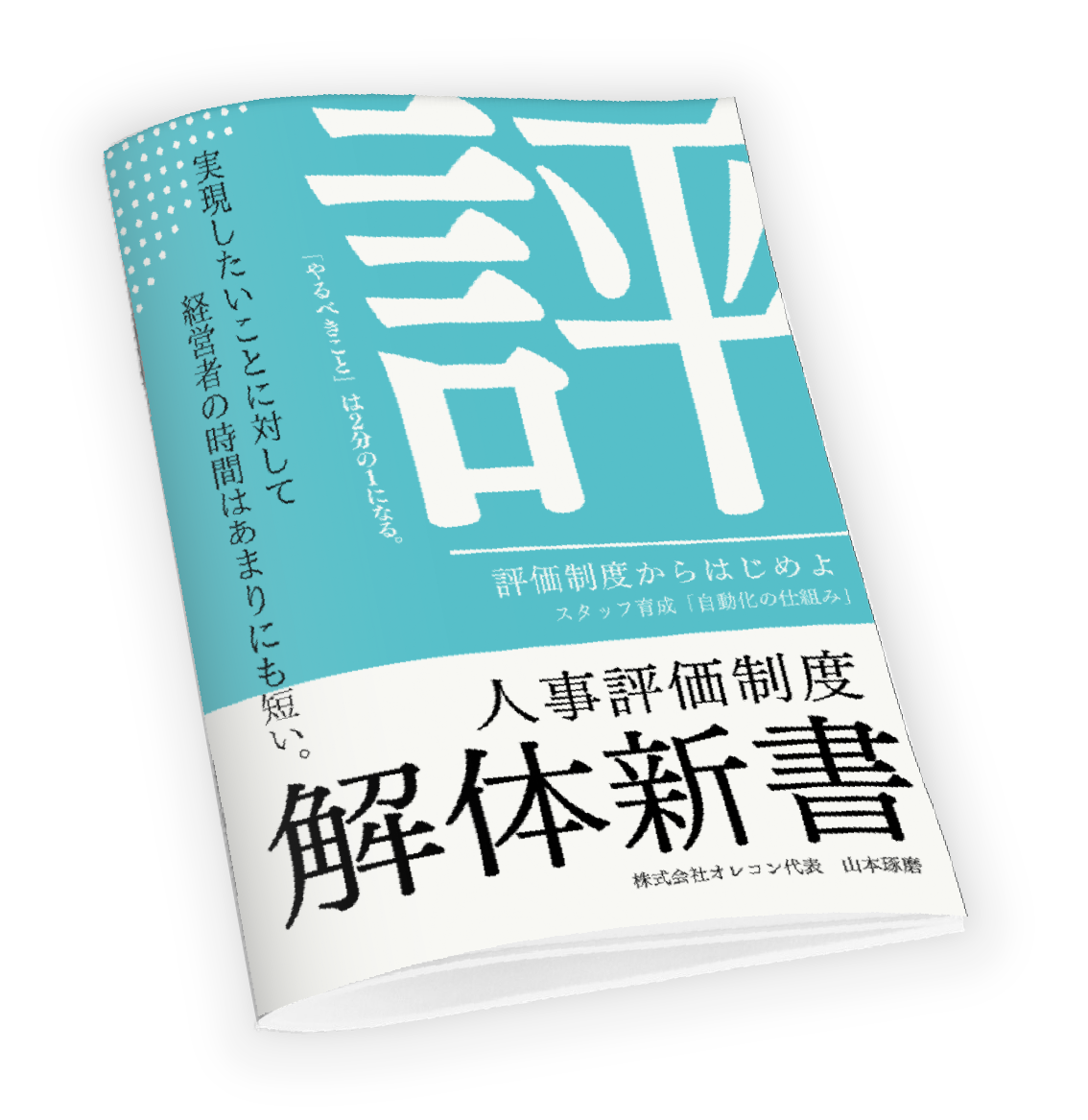
中小企業でも簡単に!
人材が定着し、成果を出す仕組みの作り方
自動で成長する会社へ!実績に基づく評価制度と仕組みを公開中