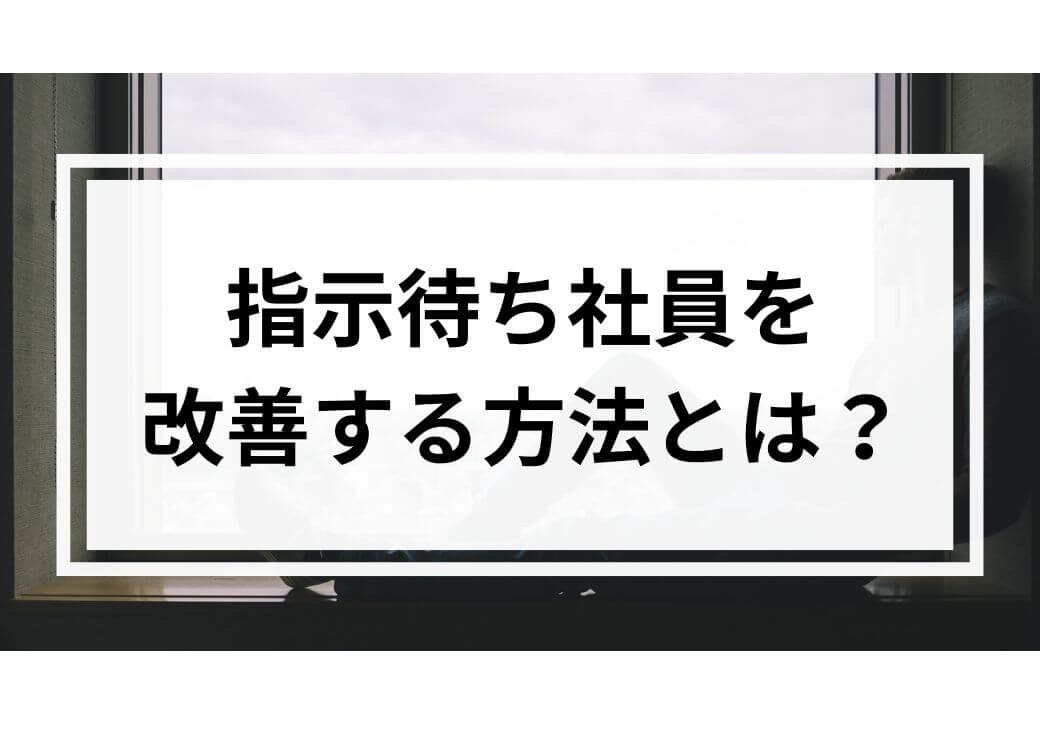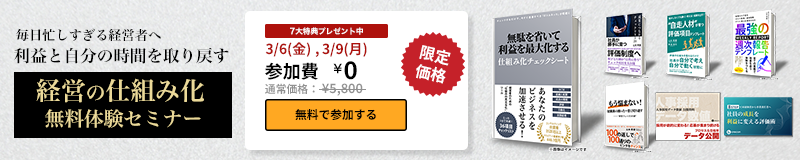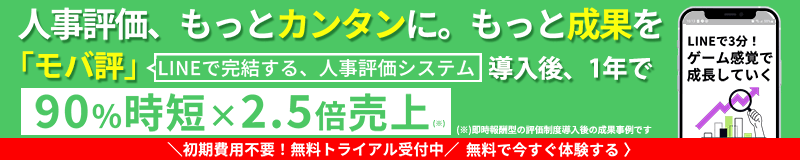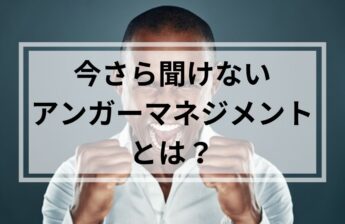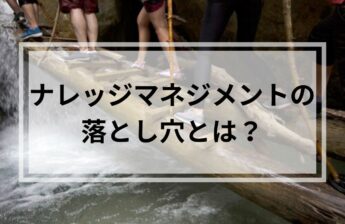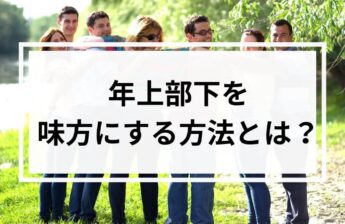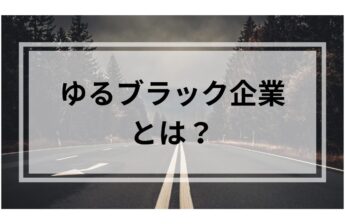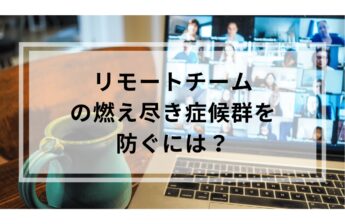指示待ち社員が生まれる背景とその影響
指示待ち社員が増える背景には、企業の組織文化や上司のマネジメントスタイルが大きく影響しています。例えば、トップダウン型の経営スタイルでは、すべての決裁が上司経由となり、社員が自ら考えて行動する機会が減少します。
その結果、社員は「言われたことだけやればいい」という受け身の姿勢になりがちです。

指示待ちになりやすい社員の特徴
指示待ちになりやすい社員には、いくつかの共通点があります。事前に特徴を把握しておけば、その社員に合った適切なアプローチが可能になり、早めに対策を講じることができるでしょう。
- 判断に自信がないタイプ:自分の決定に不安を感じ、「間違えたくない」という心理が働くため、指示を待つ傾向が強い。
- 過去の環境に影響されているタイプ:前職や社内の風土で「指示通りに動くことが評価される」と学習し、自発的に動く習慣がない。
- 責任を避けるタイプ:「指示通りに動けば責任を問われない」と考え、リスクを負うことを避ける。
- 完璧主義なタイプ:「100%正しい答え」を求めすぎて自ら行動できない。
- 受け身のコミュニケーションタイプ:指示を受けることに慣れており、意見を求められても積極的に発言しない。
指示待ち社員の問題点
指示待ち社員が企業に与えるデメリット
指示待ち社員が増えると、業務のスピードが低下し、組織全体の生産性に悪影響を与えます。
また、上司やリーダーが細かい指示を出すことに時間を費やし、本来の業務に集中できなくなるという問題もあります。
さらに、指示待ち社員の存在は、周囲の社員のモチベーション低下を招き、社内の不満が高まる可能性も考えられるでしょう。
指示待ち社員の年齢層(30代・40代・50代)による違い
指示待ち社員の傾向は年齢によって異なります。
30代は経験が浅いため、「何をすればいいのか分からない」と戸惑うことが多く、明確な指示を求めてしまいます。
40代は過去の成功体験に固執し、「これまでのやり方が最善」と考えるため、新しい方法を試すことに消極的になりがちです。
50代は長年の経験から「余計なことをしないほうが無難」と判断し、リスクを避ける傾向が強くなります。
さらに、役職や立場によっても指示待ちの理由は異なり、30代は「上司の意図を読み違えたくない」、40代は「評価が変わるのを避けたい」、50代は「波風を立てたくない」と考えやすい傾向があります。
年齢に合わせた対応も必要です。
指示待ち社員が優秀になる可能性は?
指示待ち社員も、適切な環境と指導があれば優秀な人材へ成長する可能性があります。思考力や判断力が未熟なだけで、スキルや知識が不足しているわけではないケースも多いためです。
特に、責任感が強く、指示を正確に実行できるタイプの社員は、自主性を促す機会を増やすことで大きく成長します。
また、「失敗を恐れる」「完璧主義」などの心理的要因が指示待ちの原因になっている場合、小さな成功体験を積み重ねることで自信をつけ、主体的に行動できるようになることもあります。
指示待ち社員を適切にサポートすれば、的確な判断力を持ち、自ら動ける優秀な人材に変わる可能性は十分にあるでしょう。
指示待ち社員が生まれる主な要因
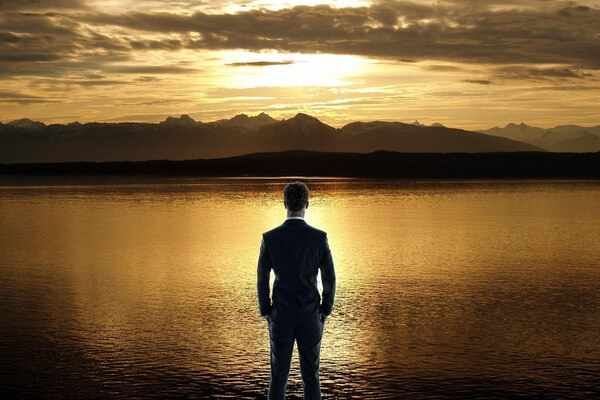
育成環境の問題:新人が指示を待つ理由
新人が指示を待つのは、経験不足と環境要因が大きく影響しています。業務知識が乏しく、何をすべきかわからないため、自分で判断する自信が持てません。
また、間違えることへの不安が強い場合、「失敗すると怒られる」「評価が下がる」と思い込んで指示を待つ傾向が強まります。
さらに、主体性を求められない環境では、自ら動く機会がなく、指示を待つことが当たり前の行動になってしまいます。しかし、育成方法に工夫を加えることで、自発的に行動する力を身につけさせることが可能です。
新人社員の効果的な育成方法については、こちらの記事もご覧ください。
企業の文化と上司の影響
企業文化と上司のマネジメントも、指示待ち社員の形成に大きな影響を与えます。
トップダウン型の文化では、決定権が上層部に集中し、社員が自ら判断する機会が減少してしまいがちです。また、失敗を許さない環境では、社員は「ミスを避ける」ことを優先するため、指示待ちの姿勢が強まってしまうのです。
上司の関わり方も重要で、細かすぎる指示を出す上司の下では部下が考える習慣を失います。決定権が与えられない場合は、「どうせ自分で判断できない」と受け身になります。
さらに、意見を否定され続けると部下は発言を控え、挑戦する意欲を失っていく可能性があるのです。このように、企業文化と上司の行動が、社員の主体性を奪い、指示待ちを助長する要因になります。
心理的要因
指示待ち社員が生まれる背景には、個人の内面的な心理要因が深く関係していることもあります。例えば、以下のような例が挙げられます。
- リスク回避志向:「自分で判断すると責任を負うことになる」と考え、上司の指示を待つほうが安全だと感じる。
- 過去の否定的経験:以前の職場で「勝手に判断して失敗すると叱責される」と学習し、消極的な行動パターンが定着している。
- 報酬や評価の影響:「指示通り動くほうが評価される」経験が多いと、自発的な行動を取るメリットを感じにくくなる。
- 主体性を持つ機会の不足:これまで指示に従うことが前提の環境で育ち、考える習慣が身についていない。
- 意思決定への不安:「自分の判断に自信がない」「選択を間違えたくない」といった不安から、行動を控える傾向がある。
指示待ち社員を改善する具体的な方法

自発性を引き出すためのアプローチ
目標設定と自己決定感を高める方法
社員が自ら考え、行動するためには、目標設定が重要です。個人の成長につながる目標を設定し、達成する喜びを感じさせることで、自発的な行動を促せます。
また、小さなタスクでも主体的に提案させて自己決定感を高めることで、社員は自信を持って仕事ができるようになります。
フィードバックの重要性と効果的な伝え方
指示を待つ社員に対して、適切にフィードバックすることも重要です。例えば、「なぜこの判断をしたのか?」と質問し、自ら考える習慣を身につけさせましょう。
また、失敗を許容し、成長の機会を提供することで、社員の主体性を育むことができます。
放置はNG!適切なサポート方法
「自発性を重視するあまり、放置する」というのは逆効果です。適度なサポートを提供しつつ、段階的に自発的な行動を促すことが大切です。
例えば、社員の強みを活かせる仕事を任せ、責任ある仕事を与えることで、主体性を引き出すことが可能です。
指示待ちを防ぐ新人育成のポイント

仕事の進め方を教える際の工夫
新人が指示を待たずに動けるようにするためには、仕事の進め方を順序立てて具体的に伝えることが大切です。
また、タスク管理の方法を共有することで、業務の優先順位を自ら判断できるようになります。
経験豊富な社員が新人をサポートすれば、仕事の早期定着や成長を促すこともできるでしょう。
「考える力」を養うトレーニング
新人のうちから、「なぜ?」と問いかける習慣を身につけさせることで、考える力を養えます。自分で考える機会を増やすことが重要なのです。
さらに、内発的な動機づけを通じて人々がより自立した行動を取るようになる「自己決定理論」を活用し、部下の自律性を促進することで、指示待ちから自立した社員へと成長させることも可能です。
成功事例:指示待ちから脱却した社員のケース
- 業務改善提案制度の導入
ある企業では、社員の主体性を育むために業務改善提案制度を導入しました。最初は消極的だった社員も、アイデアが採用されることで自信をつけ、自発的な行動が増えました。 - メンター制度によるサポート
新人研修にメンター制度を導入した企業では、先輩社員がフォローすることで新人が指示を待たずに動ける環境が整いました。その結果、半年後には指示を待つことなく行動できる社員が増え、業務の効率化につながりました。
「指示待ち社員」からの脱却を支援する仕組み
弊社オレコンでは、社員の主体性を育み、指示待ち社員を生み出さない仕組みを作ることで、企業の生産性向上に成功しました。ここでは、その内容を簡潔に紹介します。

オレコン式評価による成長支援
オレコン式の評価制度とは、従来の「指示通りに動くことが評価される」のではなく、「自ら考え、行動したこと」を重視し、社員が受け身にならない環境を整える仕組みです。
業務プロセスや成果だけでなく、課題解決への積極性なども評価基準に含め、指示待ちではなく、主体的に動くことが報われる体制を構築します。
さらに、フィードバックを重視し、成長のための改善点や成功体験を積み重ねることで、社員のモチベーション向上とスキルアップを促します。
オレコン式の評価制度については、下記の資料を併せてご覧ください。
評価制度の仕組み化からタスク管理の標準化まで、具体的な方法を無料でご提供します。
自律的に行動できる組織作り
組織全体で自律的な行動を推奨する文化を作ることも、オレコンでは重要視しています。
まず、組織のビジョンや業務の目的を明確にし、社員が「何のために働くのか」を理解できるようにすることが大切です。
次に、業務の進め方を細かく指示するのではなく、目標や期待される成果を示し、達成までのプロセスは社員自身が考えられるようにします。
自ら考えた行動が評価される組織を作ることで、組織全体の自律性を高めることができるのです。
公平かつ客観的な採用
採用時に、自律的に行動できる人材を主観に頼らず正しく見極めるために、構造化面接を導入し、客観的な評価基準を設定しています。
効果的な構造化面接の実施方法については、こちらの記事をご覧ください。
まとめ

指示待ち社員を生まない企業文化の作り方
指示待ち社員を生まない企業文化を作るためには、組織全体で主体性を尊重する考え方を根付かせることが重要です。
そのために、まず企業のビジョンを明確にし、社員が自分の役割を理解しやすい環境を整える必要があります。また、誰もが意見しやすく、挑戦しやすい雰囲気を作ることで、自発的な行動を促せます。
さらに、評価制度を工夫し、受け身の姿勢ではなく、主体的な行動が適切に評価される仕組みを作ることが効果的です。
上司と部下の関係性も重要で、一方的に指示を出すのではなく、対話を通じて社員が自分で考える習慣を身につける機会を増やすことが求められます。
人材育成とマネジメントの重要性
指示待ち社員を生まないためには、人材育成とマネジメントの改善が不可欠です。
適切な教育とフィードバックを通じて社員の主体性を育み、評価制度を工夫することで、自ら考え行動する意識を醸成できます。
また、上司のマネジメントスタイルを見直し、意思決定の機会を増やすことで、組織全体の生産性とモチベーション向上につながります。
今すぐ取り組める改善策
- 小さな決定を任せる:いきなり大きな責任を負わせるのではなく、日常業務の中で意思決定をさせる機会を増やす。
- 「なぜ?」を問いかける習慣を作る:社員に考えさせる質問を投げかけ、自発的な思考を促す。
- 定期的なフィードバック:個別に課題や目標を設定し、フィードバックを行う。
- 成功体験を積ませる:小さな成功を積み重ねることで、自信を持たせ、主体的な行動を促す。
指示待ち社員を減らすためには、企業文化の改善や適切な指導が必要です。
評価制度の見直しや育成環境の整備を進めて、社員の主体性を高め、組織全体の成長につなげましょう。
参考:
BizHint:指示待ち組織が活性化した理由。27年の現場経験が教えてくれたリーダーの鉄則
ヒョーカラボ:指示待ち人間をうむ上司の特徴4選!事例ごとの改善策を解説
Roronto:指示待ち人間は何が悪い?理由から組織での育成方法の成功事例を紹介
マイベストプロ神戸:指示待ち社員が激変!-「自ら考えて動く」チームを作るリーダーの秘密-
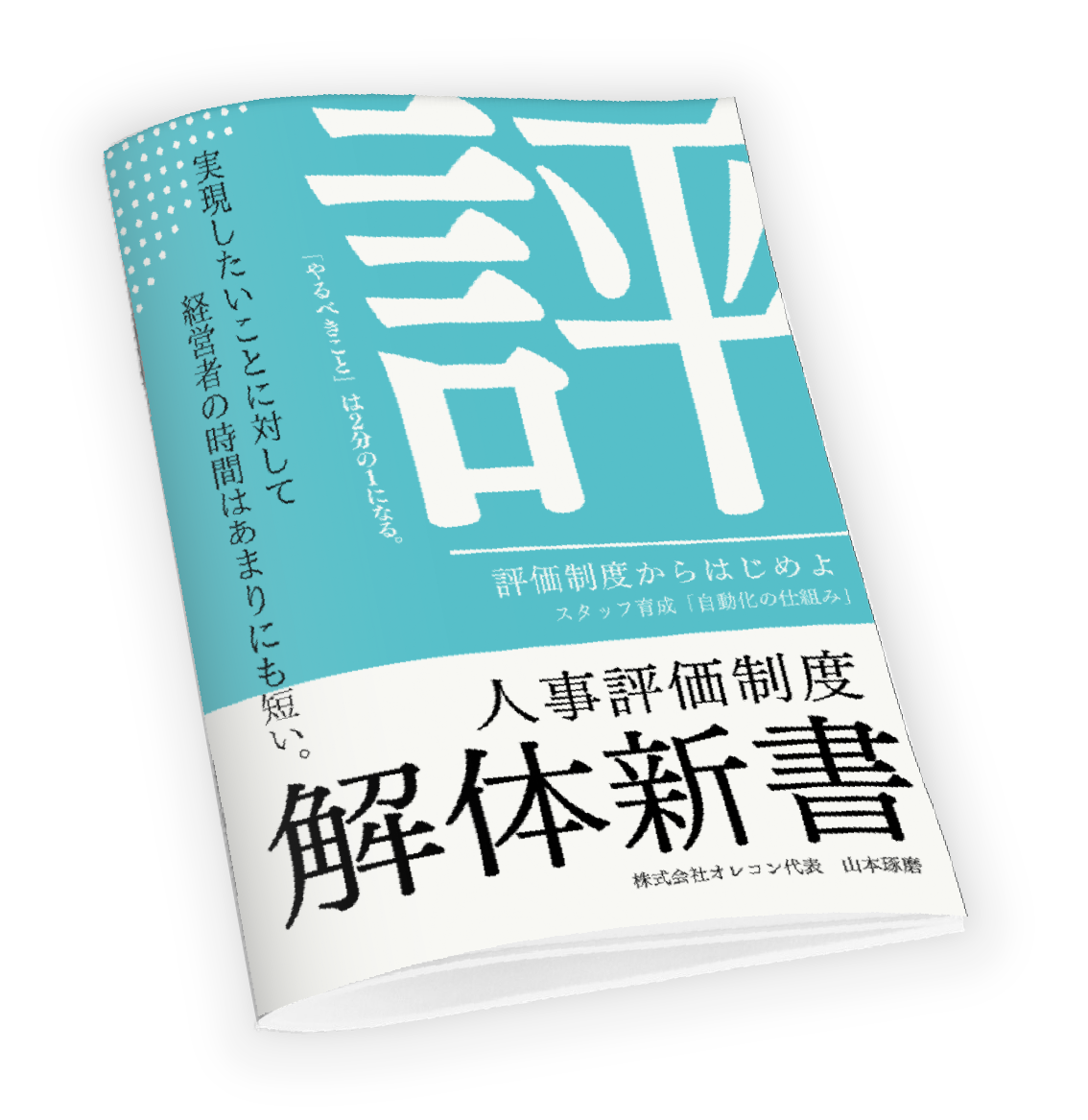
人材が定着し、成果を出す仕組みの作り方