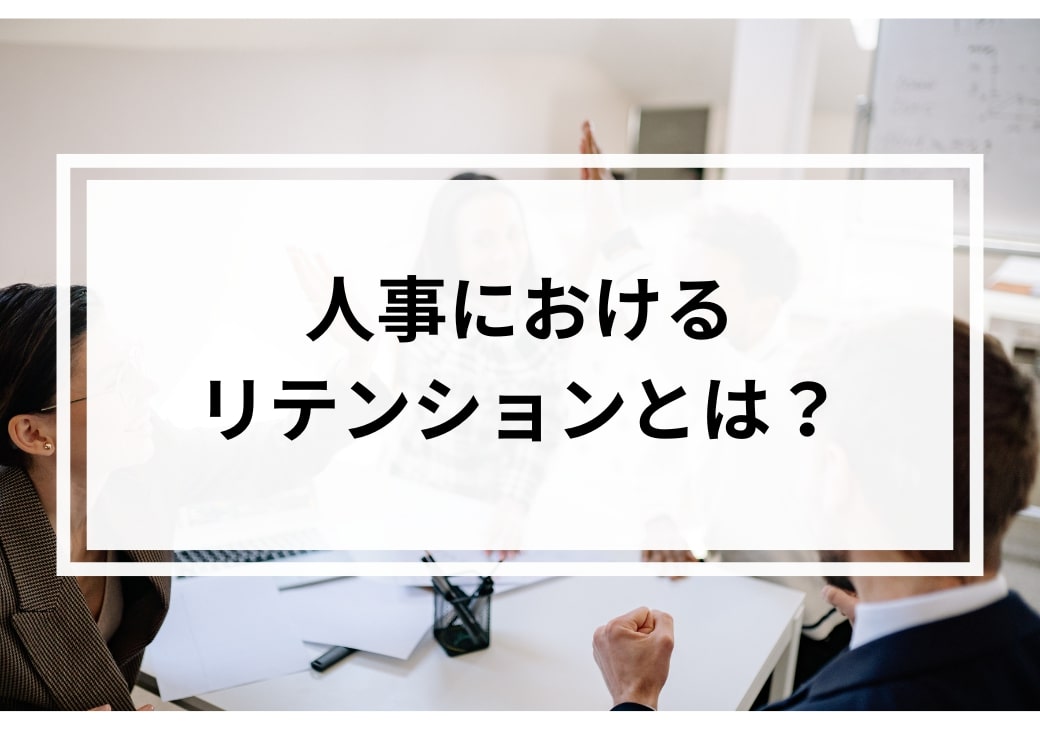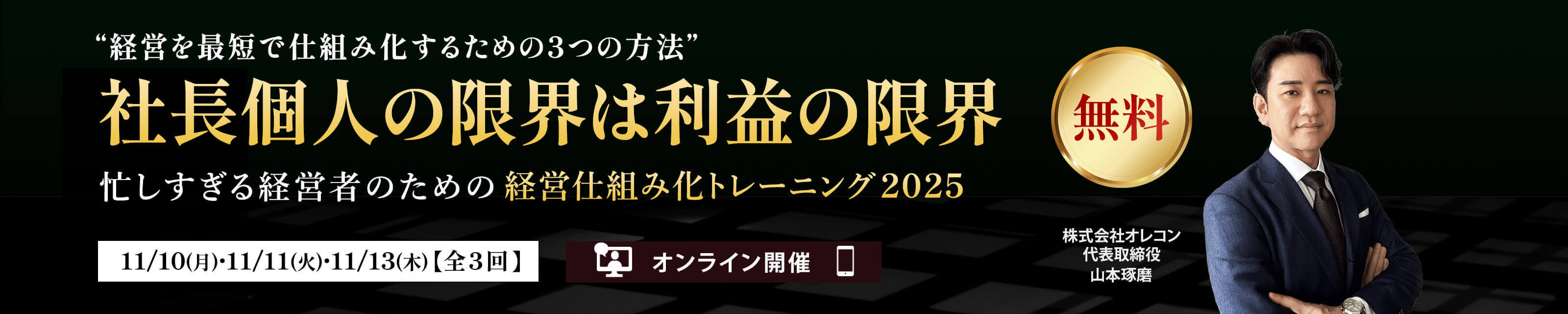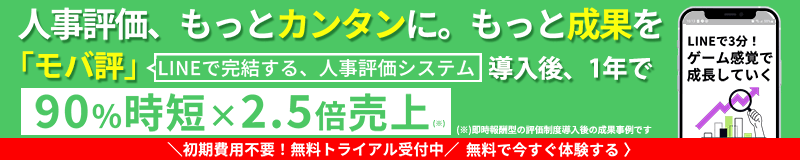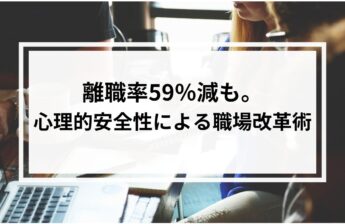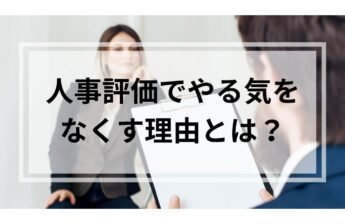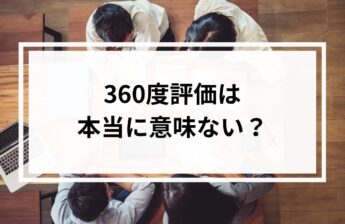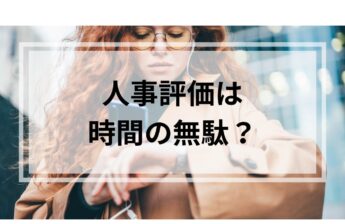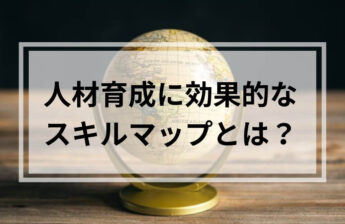リテンションとは?人事で注目される理由とその重要性

リテンションとは、直訳すると「保持」「維持」を意味する言葉です。
ビジネスの現場では、主に顧客や社員といった「重要な資産をいかに維持するか」という意味で使われています。
なかでも人事領域では、「優秀な人材が長く働き続けてくれる状態」を指して、リテンションという言葉が注目されています。
ビジネスにおける「リテンション」の具体的な使い方
たとえばマーケティングでは「顧客リテンション」という言葉が使われます。これは、一度商品を購入してくれたお客様に何度もリピートしてもらうことを意味します。
人事の分野ではこれが「従業員リテンション」となり、優秀な社員が離職せずに活躍し続けてくれるような環境づくりを指します。
単に離職率を下げるのではなく、社員のやる気やエンゲージメントを引き出すことも含めて考えるのが特徴です。
リテンションが人事分野で重要視される背景
採用が難しくなっている今、「入れること」よりも「辞めさせないこと」に力を入れる企業が増えています。
その背景には、いくつかの要因があります。
まず、少子高齢化の影響で働き手の絶対数が減っていることです。特に若手人材の確保は年々厳しくなっており、都市部でも中小企業の求人に対する応募数は大きく減少しています。
加えて、求職者の価値観も変化しています。「給与が高いから」「家が近いから」だけでは選ばれにくくなり、職場の雰囲気や柔軟な働き方、自己成長の機会などが重視されるようになりました。こうした多様なニーズに応えられない企業は、なかなか人が集まりにくいのが現実です。
特に中小企業では、ひとりの退職が売上や業務効率に大きな影響を及ぼすことも少なくありません。
また、採用・教育にかけたコストが回収できる前に社員が辞めてしまうと、大きな経済的損失にもつながります。
こうした背景から、今あらためて「社員に長く活躍してもらうための取り組み=リテンション」が経営戦略の一部として注目されているのです。
リテンションを高めるための実践的な方法

社員が長く働き続けてくれる組織には、共通して「働きやすさ」と「働きがい」の両立があります。ここでは、リテンションを高めるために中小企業でも実践しやすい施策を見ていきましょう。
社員のエンゲージメントを高める施策とは?
リテンション向上に直結するエンゲージメントの重要性
社員のやる気や主体性を引き出す「エンゲージメント」は、リテンションと深く関係しています。エンゲージメントが高い社員は、組織に対する信頼感や貢献意欲が強く、離職しづらい傾向があります。
エンゲージメントを高めるには、「会社が自分をきちんと見てくれている」と実感してもらうことが大切です。
そのためにまず取り組みたいのが、フィードバックの質と頻度を見直すことです。
社員へのフィードバックと評価システムの改善
日々の業務に対する声かけや、小さな成果を認めるフィードバックは、社員のモチベーションに大きく影響します。
「成果が出たときだけ褒める」「年に1回の評価面談だけで済ませる」ようなスタイルでは、社員は孤立感を抱きやすくなります。
また、評価制度が曖昧だったり、不公平だと感じられたりすると、社員の不満は積もっていきます。そうなると、離職に直結してしまうことも少なくありません。
評価基準を明確にし、日頃からのコミュニケーションの中で「あなたの頑張りを見ている」という姿勢を示すことが大切です。これだけでも、リテンション向上につながる第一歩になります。
エンゲージメントを高める方法についてこちらの記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
離職のリスクを防ぐには?

リテンションを高めるためには、社員が離れていく兆しに早く気づくことが欠かせません。問題が表面化してから対処しようとしても、すでに手遅れになっている場合もあります。
ここでは、離職につながる前兆を見極めるポイントと、リスクを最小限に抑えるための考え方をご紹介します。
離職リスクのサインを見逃さないポイント
「なんとなく元気がない」「最近、言動に変化がある」そうした違和感は、放っておかずに丁寧に確認することが大切です。
たとえば、以下のようなサインは注意すべき兆候といえます。
- 急に遅刻や早退が増える
- 発言や質問が少なくなる
- 業務のスピードや質が落ちる
- 雑談やランチの誘いを断ることが増える
こうした変化が続いた場合は、本人が不安や不満を抱えている可能性が高いと考えられます。
「調子はどう?」と軽く声をかけるだけでも、早めの対処につながることがあります。日頃から社員の様子に目を配り、気軽に話しかけられる雰囲気をつくることが、リテンションを支える第一歩です。
メンタルヘルスやワークライフバランスのサポート
近年は、心の健康や生活とのバランスを重視する働き方が注目されています。特に中小企業では、人手不足の影響でひとりの負担が大きくなりやすく、気づかぬうちに無理をしてしまうケースも少なくありません。
メンタルの不調や家庭の事情など、個々の事情に寄り添った対応が求められます。定期的な面談やアンケート、ストレスチェックの導入はもちろん、業務量や勤務時間の見直しも効果的です。
社員が「ここで長く働きたい」と思えるかどうかは、制度以上に日常の姿勢に現れます。小さな気配りの積み重ねが、離職を防ぎ、強い組織づくりへとつながっていきます。
リテンションが低い組織の特徴と改善策

「人が定着しない」「採用してもすぐ辞める」そう感じている場合、組織そのものにリテンションの課題があるかもしれません。
社員のやる気が持続せず、いつも人手不足を感じている状態が続いているなら、一度、組織の評価制度やマネジメント体制を見直してみるタイミングです。
リテンションが低い場合の影響
リテンションが低い職場では、次のような悪循環が起こりやすくなります。
- 採用・教育にかけた時間とコストが毎回リセットされる
- 現場の社員に業務が偏り、不満や疲労感が高まる
- 顧客対応の質が安定せず、信頼が損なわれる
その結果、残った社員のモチベーションも低下し、新たな離職を呼び込むという負の連鎖に陥ってしまうこともあります。
このような状況を防ぐには、社員一人ひとりが納得感を持って働ける「評価の仕組み」が不可欠です。
解決策としてのオレコン式評価と活用事例
社員の定着率を高め、不満の声を減らすために、株式会社オレコンでは独自の人事評価制度「オレコンWAY」を導入しています。
全職種共通のチェックリスト式評価基準を導入し、誰もが「自分が何を評価されるのか」を明確に理解できるようにしています。
また、制度は一方通行ではなく、毎年の「改善ミーティング」で社員の声をもとに見直されるため、形骸化しません。
こうした仕組みの導入によって、オレコンでは定着率が25%から67%へと改善しました。
評価制度は単なる査定ではなく、「ここで働き続けたい」と思わせる信頼の土台になり得るのです。
オレコン式評価制度をもっと知りたい方は下記の資料もご覧ください。
評価制度の仕組み化からタスク管理の標準化まで、具体的な方法を無料でご提供します。
リテンションの効果を最大化する「オレコン式」アプローチ

オレコンでは、「採用して終わり」ではなく、入社後の育成・評価までを一貫して設計することで、社員の定着と活躍を支える体制を整えています。
オレコン式評価の特長と他社との違い
オレコン式の評価制度では、全職種に共通するチェックリスト形式の基準が設定されています。その結果、社員は「今どこにいて、次に何を目指せばいいのか」を具体的に把握できるようになりました。
多くの企業では、評価基準があいまいで担当者の主観が入りやすいという点が、大きな課題です。それにより、努力しても正当に評価されていないと感じる社員が増え、モチベーションの低下や離職につながるケースも見られます。
一方、オレコンでは、給与や評価プロセスが社内で公開されており、不公平感を抱きにくい環境が整っています。制度は毎年、社員の意見をもとに見直されるため、柔軟な運用が可能です。
評価を通じて信頼関係が深まり、納得感のある組織づくりが進んでいく。この姿勢が、オレコン式の大きな特長といえるでしょう。
社員のやる気を引き出す独自評価システムの紹介
オレコンの評価制度は、「頑張りがちゃんと見てもらえている」と実感できるように工夫されています。とくに特徴的なのが、評価の進め方がわかりやすく、まるでゲームのように楽しんで取り組める点です。
社員は自分の役割に応じて、チェックリストにそって課題をクリアしていきます。それぞれの達成が評価や昇給につながるため、まるでレベルアップしていく感覚が得られる仕組みです。
「次はここまでできるようになろう」と自然に目標ができるため、日々の業務にも前向きに取り組めるようになります。
また、売上などの数字だけでなく、仕事への姿勢や仲間への協力といった“見えにくい頑張り”も評価の対象です。そのため、「自分のことをきちんと見てもらえている」と社員が感じやすくなり、やる気が高まるのです。
新人でも最初から評価のチャンスがあるため、前向きな働き方を維持しやすくなります。
こうした設計により、組織全体にポジティブな空気が広がりやすくなります。やる気を引き出すには、評価される実感と、未来への期待が欠かせません。
実際に成果を出した企業の事例
オレコンでは、この制度を取り入れたことで、売り上げは7倍、社員の定着率が25%から67%に上がりました。
評価のルールがわかりやすく、がんばりが見える形で認められるため、「ここで働き続けたい」と思う社員が増えています。信頼できる環境で、自分の成長が実感できる職場には、人が自然と残っていきます。
オレコンのような取り組みは、人手不足や離職に悩む中小企業にとって、大きなヒントになるはずです。
オレコン式評価制度については、下記の資料をあわせてご覧ください。
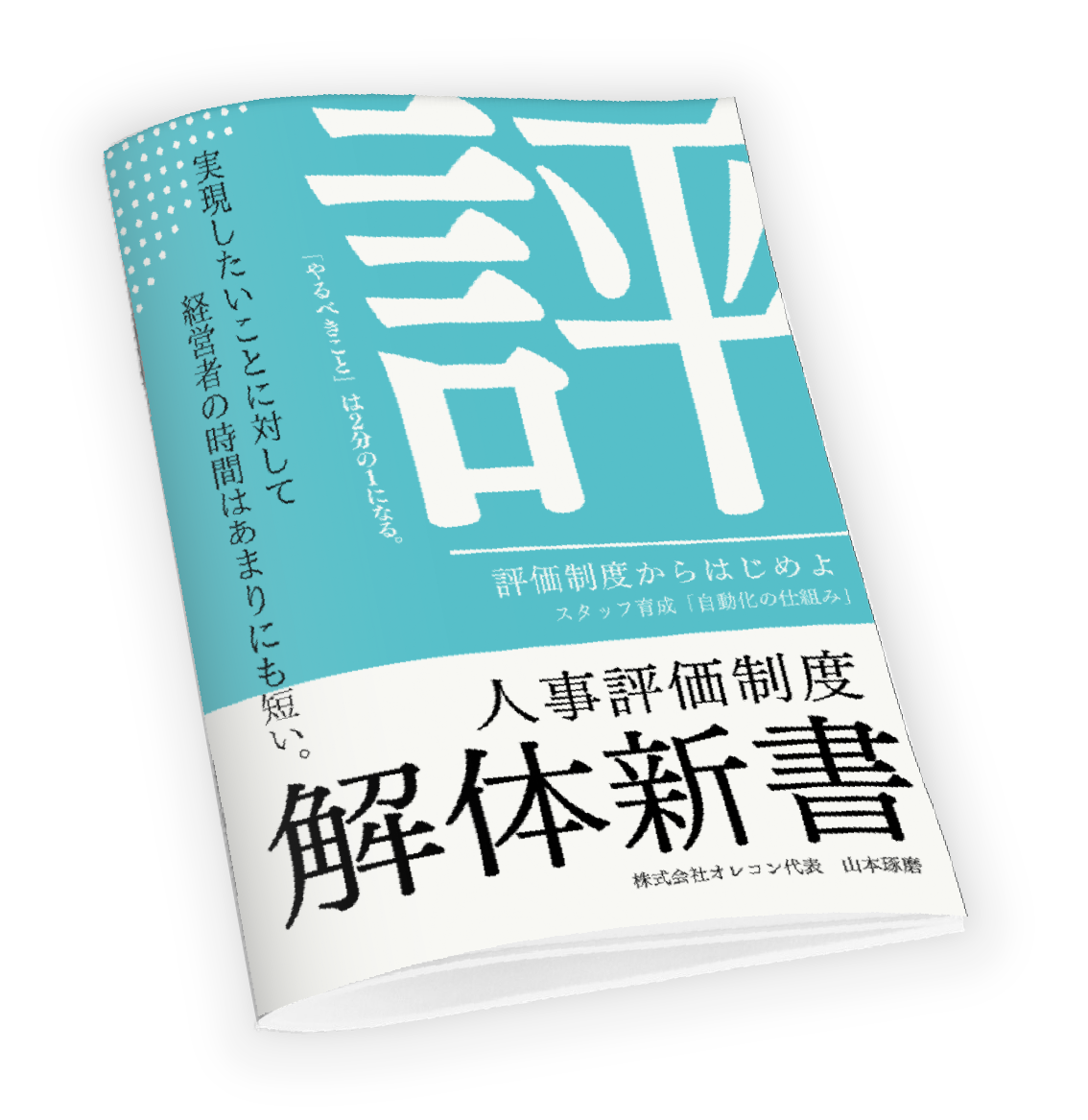
人材が定着し、成果を出す仕組みの作り方




リテンション率を継続的に向上させるための施策

評価制度や環境づくりを一度整えても、それだけで定着率がずっと維持されるとは限りません。社員の気持ちや職場の状況は日々変わるため、定期的な振り返りと改善が必要です。
ここでは、リテンションを継続的に高めるために実践したい3つの取り組みをご紹介します。
定期的な組織診断の活用方法
職場の雰囲気やチームの状態は、数値で見えづらいことが多く、感覚だけに頼ると問題に気づくのが遅れてしまいます。そこで役立つのが、定期的な組織診断です。
たとえば、年に1〜2回、社員に向けた簡単なアンケートを実施することで、今の職場の「温度感」を確認できます。診断内容は、上司との関係、仕事のやりがい、将来への不安など、幅広い項目に触れるのが効果的です。
結果はチームごとに集計し、全体の傾向と個別の課題を把握することで、次のアクションを明確にできます。小さな声に早く気づけることが、大きな離職を防ぐことにもつながります。
社員満足度調査とその分析方法

満足度調査は、「今の働き方にどれだけ満足しているか」を数値で確認できる手段です。定期的に実施し、その結果をもとに改善策を検討することで、組織の健全さを保ちやすくなります。
調査では、5段階評価やフリーコメントを組み合わせると、表面だけでなく本音にもアプローチできます。
重要なのは、調査して終わりにしないことです。結果をもとに「具体的に何を変えるか」を社内で共有し、実行することが信頼につながります。
たとえば、「会議が多すぎる」「評価のタイミングが遅い」といった声があれば、それをもとに仕組みやルールを見直してみると良いでしょう。
定点的に同じ設問を続けることで、変化も見えてきます。前回よりもスコアが上がった項目があれば、その改善策を他チームに展開するなど、好循環をつくることも可能です。
リテンションマーケティングとの連携アイデア
もともと「リテンションマーケティング」は、既存のお客さまに継続的に関わり続け、ファンになってもらうためのマーケティング手法です。
これを社内に応用すると、「社員にとっての会社のファン化」を促す効果が期待できます。
たとえば、社内での評価制度や働き方改革の取り組みを、メールマガジンや社内報などで“ストーリーとして”定期的に発信することが大切です。
単に「制度を説明する」のではなく、「なぜ取り組むのか」「誰がどう変わったのか」といったエピソードを交えて共有することで、社員の共感が生まれやすくなります。
また、社外向けに企業のビジョンや社員インタビュー、育成方針を発信することも有効です。自分が働く会社の取り組みが外部でも注目されていると知ることで、社員自身の誇りや帰属意識が高まります。
こうした「情報を定期的に届け続ける姿勢」が、社内外からの信頼を育み、リテンションの土台になります。
人事施策とマーケティングを分けて考えるのではなく、「ファンづくり」という視点でつなげていくことが、これからの組織には欠かせません。
リテンションを理解し、持続可能な組織を目指そう

本記事のまとめ:リテンションの重要性を再確認
社員がすぐに辞めてしまう状況は、採用の難しさだけでなく、組織全体のパフォーマンスにも大きな影響を与えます。
そのため、リテンションは「人手不足を防ぐ手段」ではなく、「働きやすい環境づくりを通じて、社員の力を引き出すための考え方」として捉えることが大切です。
オレコンの事例でも見たように、評価の透明性や日々のフィードバック、そして情報の共有が、社員の信頼を生み出しています。
離職を防ぐ仕組みは、結果として、やる気や成長を支える力にもなっていくのです。
長期的視点での人材マネジメントの必要性
短期的な対策では、根本的な定着率の改善は望めません。むしろ、「働き続けたいと思ってもらえる職場」をどう作っていくかという視点が、今後ますます重要になります。
そのためには、制度を導入して終わりにせず、現場の声を定期的に拾いながら柔軟に改善していくことが必要です。
働く人の価値観やライフスタイルが多様化する中で、会社としても“進化し続ける姿勢”が求められる時代です。
リテンションの取り組みは、会社の信頼づくりとブランディングの一部でもあります。
外部からの見え方だけでなく、内部の納得感を大切にするマネジメントが、持続可能な組織の土台となるのです。
次に取り組むべき具体的なアクション
まずは、社員が「自分のがんばりをわかってくれている」と感じられるような評価制度を整えることから始めてみましょう。
すでに制度がある場合は、その運用方法や社員の受け取り方に目を向けて、改善の余地がないか確認してみてください。
加えて、社員アンケートや1on1などを活用して、定期的に本音を聞ける場をつくっていくことも重要です。小さな声を拾い、具体的に改善していくプロセスが、社員との信頼関係を深めていきます。
もし、制度や仕組みの見直しに迷う場合は、他社の取り組み事例を参考にしながら、自社に合ったスタイルを模索していくと良いでしょう。
今日からできる一歩を積み重ねることで、社員が安心して働き続けられる環境が育っていきます。