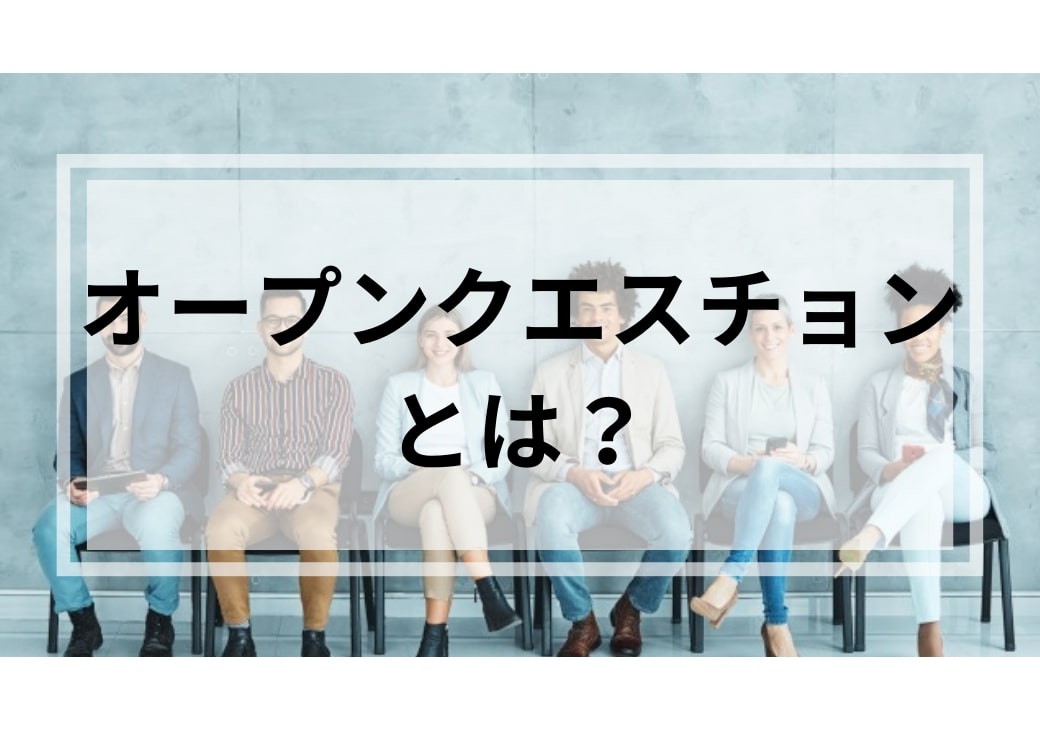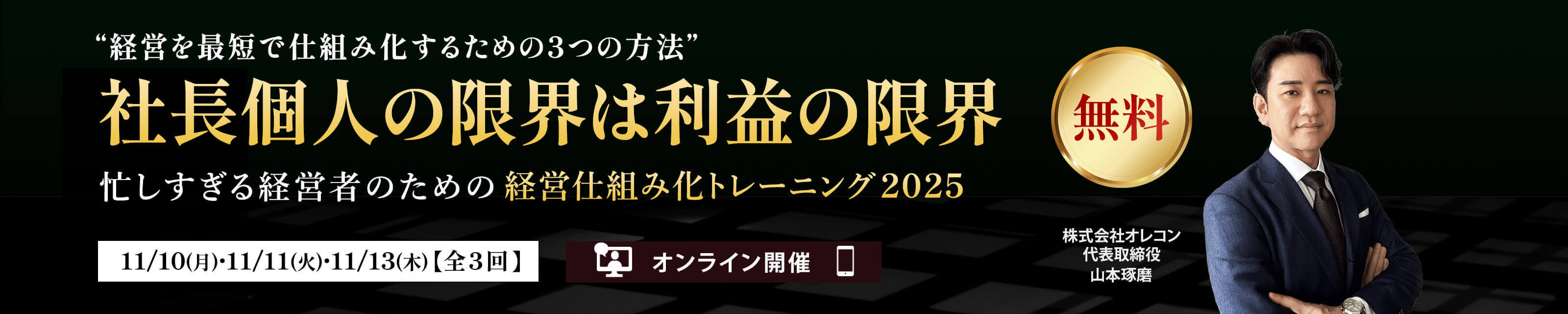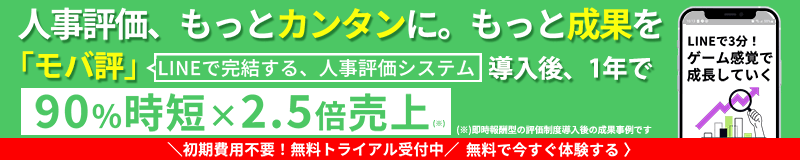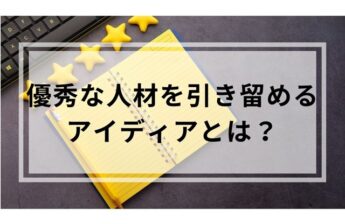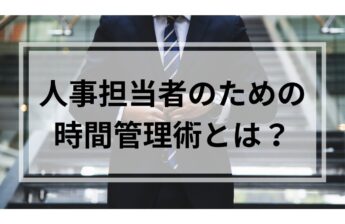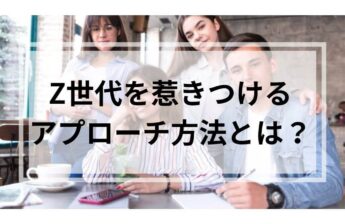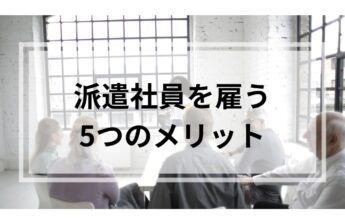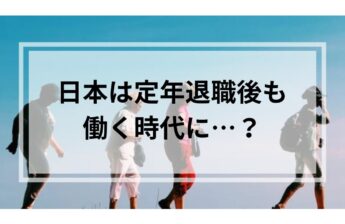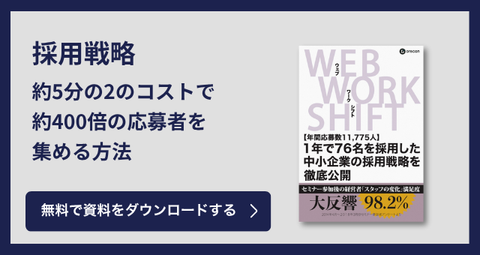オープンクエスチョンとは?
オープンクエスチョンとは、回答者に自由な範囲で答えてもらうための質問方法です。
つまり、特定の正解を求めるのではなく、自分の意見や考えを自由に表現してもらうための質問です。
例えば、以下のような質問がオープンクエスチョンになります。
・好きな趣味は何ですか?
クローズドクエスチョンとは?
オープンクエスチョンとセットにされるのが、クローズドクエスチョンです。
クローズドクエスチョンとは、回答者に自由な答えを求めるオープンクエスチョンとは違って、「Yes(はい)」か「No(いいえ)」という形での回答を求める質問方法です。
例えば、以下のような質問がクローズドクエスチョンになります。
・今日の天気は晴れですか?
面接でオープンクエスチョンを活用するメリット
採用面接でよく取り入れられるオープンクエスチョンですが、どのようなメリットがあるのでしょうか?
候補者の個性と能力をより詳しく知ることができる
オープンクエスチョンは回答者に自由な意見や経験を共有させるため、候補者の個性や考え方を深く理解することができます。
面接では、単なる経歴やスキルだけでなく、その人の人間性や適性を把握するのに役立つでしょう。
コミュニケーションスキルの評価が可能
オープンクエスチョンは、回答者が自分の意見を明確に伝えることを要求します。これにより面接では、コミュニケーションスキルや表現力を評価することができます。
したがって、適切な言葉で自分の考えを伝えることができるかどうか判断できる要素となるでしょう。
問題解決能力を見極めることができる
オープンクエスチョンは、回答者が新しいアイデアを出したり、複雑な問題に対してどのように対処するかを示すチャンスを提供できます。
これにより、問題解決能力を確認することができます。
自己分析や自己理解が促進される
これは、回答者側のメリットになりますが、回答者はオープンクエスチョンを通して自分自身を振り返る機会が得られます。
自己分析や自己理解が促進され、自分の強みや成長すべき点を自覚できるでしょう。
採用面接でオープンクエスチョンを取り入れることで、候補者の個性や能力をより深く理解することができます。
さらにオープンクエスチョンを通して、コミュニケーションスキルや問題解決能力などを確認でき、優秀な人材を見極めるのに役立つと言えるでしょう。

オープンクエスチョンのデメリット
オープンクエスチョンはメリットだけでなく、もちろんデメリットもあります。
それでは、オープンクエスチョンのデメリットをいくつか紹介しましょう。
面接される側の負担が大きい
オープンクエスチョンでは自由に回答できるため、「どんな答えを出そうか」と考える時間が必要になります。
そのため、面接される側の心理的な負担が増えることがあります。回答者は何を言おうか迷ったり、不安に感じることがあるかもしれません。
質問に対する回答にズレが生じる可能性がある
オープンクエスチョンでは、質問の意図を面接される側が正しく理解できなかった場合、質問に対する回答にズレが生じる可能性があります。
その結果、会話が予想外の方向に進んでしまったり、ヒアリングの時間が余分にかかってしまう‥という可能性も考えられます。
話が逸れることで本来の目的を見失ってしまうこともあるでしょう。
Google人事がやっている「構造化面接」とは?
世界的な大企業であるGoogleは、「構造化面接」というものを採用しています。
では、構造化面接とはどのようなものでしょうか?
構造化面接とは、同じ職務に応募している応募者に同じ面接手法を使って評価することです。構造化面接を行うことで、応募者のパフォーマンスを予測できるというメリットがあります。
中でも実際にGoogleがおこなっている構造化面接には、2種類の質問があり、その質問について、Google re:Workでは下記のように紹介しています。
あなたの行動がチームに良い影響を与えたときのことを話してください。あなたの第一目標は何でしたか?
その目標を立てたのはなぜですか?
同僚はどのように反応しましたか?
今後はどのような計画がありますか?
メールサービスを提供する業務を行なっている際、競合他社が、自社サービスに月額5ドルの課金を始めたとします。あなたは、その状況をどのように評価し、チームに何をするようにすすめますか?推奨案を伝える前にどのような要因を考慮しますか?
推奨案のメリットとデメリットは何ですか?
それが今後も持続可能なモデルかどうか、どのようにして評価しますか?
組織全体にはどのような影響があるでしょうか?
これらを見てみると、「Yes(はい)」か「No(いいえ)」で答えられるクローズドクエスチョンではなく、オープンクエスチョン形式になっていることがわかります。
これらは応募者の能力を適切に把握するために有効な手段と言えるでしょう。

採用基準の標準化と改善について、資料の中でも具体的な方法をお伝えしています。
【無料】中小企業でもできる!年間76名を採用した戦略
採用成功の鍵を手に入れよう!実績データに基づいた採用戦略を無料で公開しています。
採用基準を徹底して標準化し、仕組み化を進める方法が分かります。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを組み合わせる
オープンクエスチョンは、自分の意見や考えを最初から最後まで自分で考えて回答する必要があるため、オープンクエスチョンが続くと、回答者の負担が大きくなります。
また、クローズドクエスチョンが続くと、欲しい情報が得られなかったり、回答者に圧迫感を与えてしまいます。
しかし、オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンをうまく組み合わせることで会話の流れがとてもスムーズになるのです。
例えば、採用面接や商談など、初めて会う人とコミュニケーションをとるときです。
まずは答えやすいクローズドクエスチョンから入ります。
相手が少しリラックスできたところで、より具体的な内容をヒアリングするために、オープンクエスチョンにシフトしてみましょう。
【クローズドクエスチョン】
「新しいアイデアを出すことは得意ですか?」
【オープンクエスチョン】
「過去に出したアイデアの中で、特に印象に残るものはありますか?それはどのようなアイデアでしたか?」
「どのようにしてそのアイデアに至ったのですか?」
【クローズドクエスチョン】
「過去にプロジェクトを担当したことがありますか?」
【オープンクエスチョン】
「そのプロジェクトを担当した際、どのような課題に直面しましたか?」
「その課題をどのように解決しましたか?」
・
・
このようにクローズドクエスチョンから入ったり、オープンクエスチョンの間にクローズドクエスチョンを挟むことで相手は次の質問に備えることができます。
オープンクエスチョンが続いてしまうと回答者は疲れてしまい、こちらが得たい回答もスムーズに聞き出せないかもしれません。
クローズドクエスチョンを挟むことで、ニーズであったり、その後の成果であったりのヒアリングをスムーズに行えます。
オープンクエスチョンで従業員が成長する
冒頭でもちらっとお伝えしましたが、オープンクエスチョンをうまく活用することで、従業員の育成にも効果があると言われています。
なぜ、従業員の育成にも効果的なのでしょうか?
その謎について探っていきましょう。
例えば、プロジェクトがうまく進まず困っている従業員に「このプロジェクトの進捗状況は問題ないですか?」「事前に十分な調査はしたんですか?」「なぜ事前に言わなかったんですか?」と質問するとします。
これらはクローズドクエスチョンで、このような質問ばかりされると「責められている」と感じてしまうのです。
そうなると従業員はどうなるでしょうか?
やる気がなくなったり、相談したくてもしづらい‥と感じる従業員は多いのではないでしょうか?従業員の意見に耳を傾けること、意見を聞き出すことも上司の重要な役割です。

・プロジェクトを遂行する上で、もっとやっておけばよかったと思うことは何ですか?
・どうすればもっと良くなると思いますか?
・私にサポートできる部分(してほしい部分)はどこですか?
クローズドクエスチョンと違い、問い詰められている印象は薄くなりませんか?
そして「Yes(はい)」「No(いいえ)」だけでは答えられない質問なので、従業員は多くのことを考えるようになります。
・あのときどうすれば良かったのか?
・この状況を打開する改善策を考えよう
そしてそれを実際に言葉にする機会が増えることで、従業員が自ら改善に向けて考えるようになり、行動するようになるのです。
オープンクエスチョンをうまく活用することで、従業員のパフォーマンス向上に繋がるというわけです。
まとめ
いかがでしたか?
オープンクエスチョンは、相手の考えや意見を聞き出すのにとても有効な質問です。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを組み合わせて活用することで、優秀な人材の確保や従業員の成長に繋がります。
ぜひ、採用面接やマネジメントに取り入れてみてはいかがでしょうか?
この記事が少しでもお役に立てたら幸いです。
面接の採用判断については資料の中でも詳しくお伝えしています。こちらもぜひ一度お読みください。
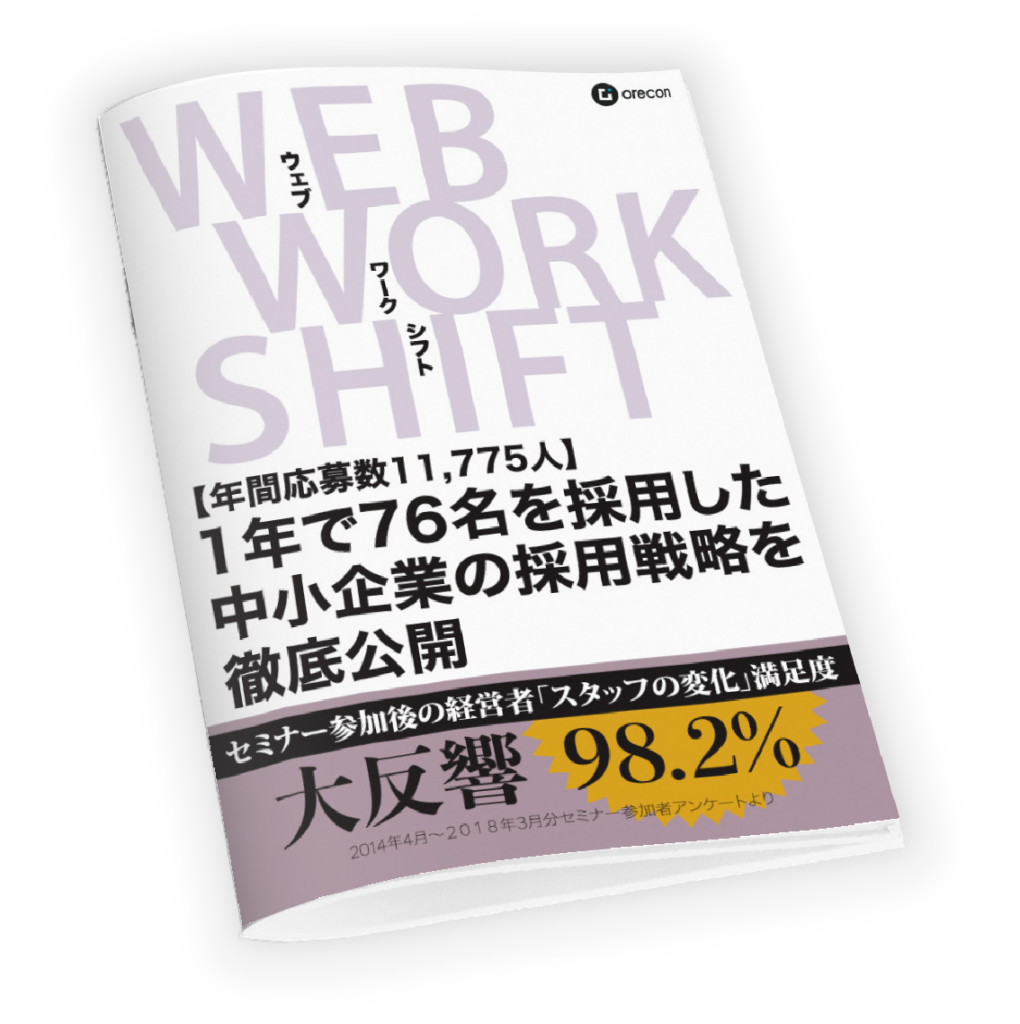
中小企業でもできる!
年間76名を採用した戦略
採用成功の鍵を手に入れよう!実績データに基づいた採用戦略を公開中




人事評価や採用についてのご相談も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。